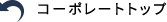自動車業界ライブラリ > コラム > ハイブリッド・システムの今後
ハイブリッド・システムの今後
◆ハイブリッド車、ダイムラーと技術供与交渉、トヨタ、開発投資を回収。
トヨタ自動車が独ダイムラーとハイブリッド車の技術供与に向け交渉に入った。実現すればトヨタにとって同分野で4社目の技術供与となり、基幹部品の供給も検討する。ハイブリッド車販売の主戦場は新興国にも広がり、価格競争も激しさを増す。トヨタは他社への技術供与や部品供給を通じて開発や生産投資を早期に回収、ハイブリッド車の普及加速へ低価格化を急ぐ。
<2010年 09月 17日 日本経済新聞>
◆独ダイムラーの社長、トヨタと成果急がず。
ツェッチェ社長は、パリ国際自動車ショーの記者会見で、トヨタと環境車分野で提携するとの見方について、「トヨタとは長年話し合いをしているし、今後も続けると思うが、短期間で特定の成果が得られるとは期待していないし、得られないかもしれない」と語った。
<2010年 09月 30日号掲載記事>
◆ソニー、TomTom社のリアルタイム交通情報サービスを欧州向けカーナビに
欧州で 2DIN サイズのインダッシュ型カーナビの新製品「XNV-l77#BT」「XNV-l66#BT」を発表。オーディオ機能をソニーが、カーナビ機能をオランダの TomTom 社が開発。TomTom 社の「Live services」と呼ぶリアルタイム交通情報サービスをはじめとした各種機能を利用できる。端末に内蔵した GPRS(General Packet Radio service) 通信モジュールを使い、3分おきに最新の渋滞情報や事故情報を入手できるほか、速度監視カメラや事故多発地点の警告、Google社の検索エンジンによるホテルやレストランなど周辺情報の検索機能も利用できる。
<2010年 09月 23日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【欧州メーカーから見たハイブリッド・システム】
私事で恐縮だが、筆者は欧州駐在時代に、ダイムラーや BMW の駆動系設計者と新車のテスト走行に同乗したことがある。時速 300kmもの猛スピードで加速して急ブレーキをかける。どの車も停止時に車両が大きく揺れることなく、安定姿勢を保ったまま止まる。設計者は車の剛性や重量配分、ABS の利かせ方などメーカーとしての苦労話をした上で、一様に「これがドイツ車」と誇らしげに語っていた。
速度制限のないドイツのアウトバーンでは実際にこんな猛スピードで急停止することもありえる。他国では考えられない交通事情が育んだドイツ車の潜在能力と感心した。
「走る」「止まる」「曲がる」の基本性能で右に出るものはないと自信を持っていたドイツ車であったが、その設計陣が舌を巻いたものの一つが、トヨタのハイブリッド・システムだった。
内燃機関と電気モーターを組み合わせたハイブリッド車の歴史は古い。1900年ポルシェ博士はインホイールモーター式の電気自動車を作ったが、二次電池の限界に気づき、ガソリンで発電機を回して電気をモーターに供給する(今で言うシリーズ式)ハイブリッド車の開発を推し進めた。ハイブリッド車はもともとは欧州発のコンセプトである。しかし、欧州では量産化に至らず、結果としてトヨタに先を越されることとなった。
トヨタがプリウスを世に送り出した際、欧州勢は「環境車はディーゼル」と言ってあまり関心を示さなかったと言われる。しかし、それは正しい表現ではないと思う。一種の負け惜しみのような感情もあったはずである。少なくとも筆者が接した欧州のエンジニア達は大きな興味を示していた。これを活かせば、環境に優しく且つ「スポーティ」な車を作ることができる、と。
【ハイブリッド車はスポーティ?】
電気モーターのメリットは低回転域から大きなトルクを発生する所である。一例を挙げると、米テスラモーターズ社の EV ロードスター(価格約 10 万ドル)は時速 100kmに達するまでの時間がたった 3.9秒という。低回転時から400NM のトルクを発生する電気モーターのお陰である。フェラーリ 612 スカリエッティ(排気量 5.7L、価格約 20 万ユーロ)ですら 4.2秒かかる。同車は 5,250rpm時に 589NM ものトルクを発生するが、内燃機関の宿命で低速時より一気にトルクを上げられないことで、EV ロードスターに後塵を喫することとなっている。
トヨタのハイブリッド車を見て実用性を確信した欧州のエンジニアの中には、こうした電気モーターのスポーツ特性を自社の車両に応用するアイデアを持った人間もいたはずである。実際、現在欧州で発表・発売されているハイブリッド車両の多くが SUV 車である。(もちろん高価なハイブリッド機構を小型量産車に投入するには経済的に割に合わないといった背に腹はかえられぬ事情もある。)モータの動力を使ってスムーズに加速することで時速 100km以上で走行している車をエンジンへの負荷を軽減しながら軽々追い抜くことも出来るようになる。
しかし、トヨタが先陣を切り、独走を仕掛けた同社のストロング・ハイブリッド方式は、その名前の通り、余りに強すぎた感がある。動力伝達機構や配分制御等の重要技術の特許の押さえが行き届き、他社が追随できない状態になっていたと伝えられている。欧州の車両メーカーが商品の潜在力に大いなる興味を示しつつも、トヨタとの提携なしにはこの技術を使えない状態になっていたため、他の仕組みを模索してきたというのが実情と思われる。
ハイブリッドシステム自体が多様化する中で、欧州勢も大手部品メーカーの力を借りながら、自社製品にその技術を取り込みつつある。しかしながら、この分野において、トヨタを超えるシステムを確立したメーカーはまだないというのが現状であろう。
【オープン・アーキテクチャの活用】
ハイブリッド領域でトヨタの技術力は他を圧倒するものとなった。しかし、これからの市場戦略を考えていく上では、優れた技術を独占し続け、完成品の性能優位性で勝負し、その完成品の販売で収益を回収していくべきなのか、それとも、他社との連携を強化しながら、自社技術の普及拡大を目指し、ライセンス収益の獲得を狙うべきなのか、議論の分かれるところであろう。クローズで行くべきか、オープンに転じるべきか、いわゆるアーキテクチャ戦略である。
こうしたアーキテクチャ戦略を自動車業界で考える上では、その代表的かつ先行的な事例として、エレクトロニクス産業での実例から学ぶところは少なくない。
エレクトロニクス産業においても、これまで、世界最先端の技術を開発し、世界最高レベルの性能を誇る製品を投入しながら、グローバル市場においては他社・他国の製品に劣勢となっている分野も少なくない。携帯電話、液晶テレビ、DVD プレイヤー等々。
この産業において勝者となっている企業は、その戦略としてオープン・アーキテクチャを積極的に活用しているものが少なくない。インテルの CPU、アップルの iPhone、等々、頭に浮かぶ読者も多いであろう。
製品構造としてオープン型であるエレクトロニクス業界とは対極にあり、クローズ型が主流とされてきた自動車業界でもこうしたオープン・アーキテクチャを積極的に活用する企業が台頭してきている。
オランダに TomTom という会社がある。90年代に設立された後付け用ナビゲーションメーカーである。当時欧州のナビゲーションは BMW やベンツといった高級自動車メーカーが搭載し始めた頃で、非常に高価なものであった。そこに T社は格安のナビをアフターマーケット市場に投入し、ユーザーの支持を得た。現在はその成功によって得た資金で交通情報管理システムを構築し、これを経営の核として事業を拡大している。ハードを廉価で普及させた上で、ソフトやコンテンツで稼ぐ稼ぐ姿は、米アップル社の戦略にも重なる。
完成品ブランドに拘らないキーデバイスやソフト重視の戦略は今後の自動車業界、取り分け次世代自動車のビジネス・モデルの参考になろうかと思う。他社が追随できないキー・デバイスやソフトを開発し、それを広く共用化して販売する。これまで欧米メーカーが得意としてきた戦略にも学ぶところがあるはずである。
【ハイブリッド・システムの今後】
勿論、オープン・アーキテクチャ化を礼讃したいわけではない。産業構造、製品特性、品質基準等、様々な要因を分析した上で、取り入れるべきところを考えたら良いというのが、筆者の考えである。オープン・アーキテクチャのメリット・デメリット等については、以下コラムで解説しているので、興味がある読者は参照してほしい。
『インテグラルとモジュラーの共生を考える』
https://www.sc-abeam.com/mailmagazine/kato/kato0155.html
これまで、トヨタも自社のハイブリッド・システムを他のメーカーに提供することを考えてこなかったわけではない。日産、マツダ、米フォード(アイシン AW 経由)に加えて、今回のダイムラーが 4 社目の提携にあたる。
そもそも二つのエネルギー源の共用という広義な意味を持ち、その宿命として、ハイブリッド・システムそのものの多様化が進んでいる。トヨタが市場に投入して 10年が過ぎたが、技術面で独走してきたからといって、市場において独占的なポジショニングを確保し続けることは簡単ではないはずである。
仲間を積極的に増やすことで享受できるメリットも、トヨタは十分に分かっているはずである。今回の提携にあたっても、これまで通りの条件で交渉していくべきなのか、ハードルを下げてでも広がりを重視していくべきなのか、悩ましい選択に迫られていると想像する。
現時点では、両社の交渉は必ずしも順調とは言えないようである。日本の誇る一つの先進技術が、今後 10年間においてどういうポジショニングを確保できるか、大きな岐路に立っていると考える。
<櫻木 徹>