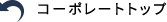自動車業界ライブラリ > コラム > インテリジェント触媒から学ぶ「技術の流動性」
インテリジェント触媒から学ぶ「技術の流動性」
◆ダイハツ、「インテリジェント触媒」を医薬品製造分野へ展開
パラジウムは、自動車用触媒以外に医薬品・化学品の製造工程における触媒として広く使用されており、「高い反応活性」と「長寿命」を両立させた『インテリジェント触媒』はこれらの分野でも非常に有用と判断、北興化学工業と共同で医薬品を中心とした化学品メーカーへ同触媒の供給を開始する
パラジウム触媒の化学品製造への応用例は、医薬品では、「高血圧治療薬(血圧降下剤)」「抗うつ剤」、電子材料では「液晶」「有機EL」。
<2005年12月12日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今更ではあるが、地球環境に優しい技術開発は、自動車業界において最も大きなテーマの一つである。大気汚染、地球温暖化、化石燃料枯渇など、様々な問題と向き合い、自動車が環境に優しい存在とならなければ、21 世紀のクルマ社会が持続的に成長していくことができないからである。
特に動力源については、ハイブリッドカーや燃料電池電気自動車など、これまでの自動車の仕組みを変える技術が登場しており、未来を支える次世代技術として注目を集めている。しかし、自動車が誕生してから 100年以上経つ現在においても、内燃機関が依然として動力源の中心的存在であり続けている。内燃機関自身が絶え間ない進化を続け、他の動力源を上回る性能を持つ存在であり続けているからである。
環境面においても、内燃機関は性能を向上させてきた。特に大気汚染が大きな問題となった 1970年代以降、排ガス性能は革新的な進化を遂げ、マスキー法を始めとする「現時点の技術では不可能」と思われた高いハードルをいくつも乗り越えてきた。
この排ガス性能の飛躍的な向上に大きく貢献してきたものの一つが、排出ガスを浄化する触媒技術である。排出ガス用の触媒とは、排出ガス中の有害物質を化学反応によって無害な物質に変えるもので、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素(HC)の三つを同時に低減させる三元触媒が主流となっている。触媒物質としては、白金、パラジウム、ロジウムの三種類の貴金属が使用され、以下の反応により、排出ガスを浄化する。
HC(炭化水素) →【酸化】→ H20+CO2(水と二酸化炭素)
CO(一酸化炭素) →【酸化】→ CO2(二酸化炭素)
NOx(窒素酸化物)→【還元】→ N2+O2(窒素と酸素)
この化学反応の効果をあげるために、これらの貴金属を微粒子状にして表面積を広げているが、数百度から千度にも及ぶ高温の排出ガスに晒されるため、熱に弱い貴金属の粒子が増大してしまい、表面積が次第に小さくなってしまう性質を持つ。したがって、触媒の浄化性能は年々低下してしまうという問題がある。
一般的に、多くの自動車メーカーは、この性能低下を見込み、貴金属の量を増やすことで排出ガスの浄化性能を維持しており、年々強化される排出ガス規制に伴い、1990年以降自動車業界での貴金属の使用量が増大している。これは、自動車メーカーにとっても大きなコスト負担となっているだけでなく、燃料電池などの次世代技術や電子・化学品業界など他分野でも使用される限られた貴重な資源であるという観点からも、貴金属の使用量を削減する技術が待望されている。
ダイハツが 2002年に実用化した「インテリジェント触媒」は、この触媒の性能低下を防ぎ、貴金属の使用量を低減する技術として注目されている。「インテリジェント触媒」は、三種類の貴金属のうち、最も劣化しやすいパラジウムに自己再生機能を持たせることで、使用量の削減を実現した。同社によると、2005年 9月末時点ですでに 150 万台の車両に搭載されているという。そして、2005年には、この技術をさらに応用し、白金とロジウムにも自己再生機能を持たせた「スーパーインテリジェント触媒」を開発している。
この「スーパーインテリジェント触媒」の開発には、ダイハツに加え、独立行政法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)、株式会社キャタラー、北興化学工業株式会社の三団体が協力している。こうした業界の壁を越えた連携が、革新的な技術を生み出す原動力となったのであろう。
そして今回、ダイハツと北興化学が、この「インテリジェント触媒」技術を自動車以外の産業分野に応用展開することを発表した。パラジウムを使用する医薬品・化学品の製造工程に応用することで、コスト、生産性、安全性を両立しようとするものである。国内だけでなく、英国の大学やベンチャーと共同で、海外の医薬品・化学品メーカーにも展開するという。
こうした取り組みを活性化させることができないだろうか。国内主要産業の研究開発費約 10 兆円のうち、約 2 割にあたる 1.8 兆円を占めている自動車産業は、日本の製造業の研究開発をもっと推進する役割を担うべきではなかろうか。毎年数千億円もの研究開発費を投入する自動車メーカー各社は、研究所を構え、先行開発を行い、ここで開発された技術が新型車に投入されている。しかし、実際に車両に投入される技術はごく一部で、多くの技術は引き続き研究開発を続けられるか、自動車には使えないとして埋もれていってしまうのが現状であろう。これを打破することができれば、自動車産業の研究開発も更に活性化するのではないだろうか。
東京大学の藤本教授の提唱するアーキテクチャ理論によると、自動車は「囲い込んで擦り合わせる」クローズ・インテグラル型に分類される。多数の機能部品が複雑に絡み合って構成されており、その一つ一つが微妙に調整されて全体の機能を発揮するからである。自動車はこうした特性を持つ製品であるため、個別の部品・技術が単体で機能を発揮するとは考え難い一面があり、こうした考え方が自動車業界の研究開発を孤立化させることにつながりかねない。
今回の事例のように、自動車以外の産業分野に目を向ければ、活用できる単体技術が多数あるのではないだろうか。IT ・バイオ分野など、異業種の技術を自動車に応用する取り組みが注目を集めており、業界間の垣根は着実に低くなってきている。自動車分野の技術でも、他の産業に応用できるものがもっと出てきても良いはずである。
昨今、エンジニアの不足、市場の多様化、電子化・ IT 化の進展などにより、自動車メーカーのリソースは慢性的に不足しており、これに伴い、エンジニアを始めとする異業種の人材を採用する動きが見られるなど、人材の流動性が高まりつつある。業界の壁を越えて既存概念に囚われずに広い視点を持ち、技術の流動性を高めることができれば、自動車業界自体の更なる持続的な成長にもつながるのではなかろうか。
<本條 聡>