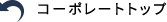自動車業界ライブラリ > コラム > 日米同盟と企業間のアライアンス
日米同盟と企業間のアライアンス
◆米 GM、保有いすゞ株を売却へ。伊藤忠や三菱商事など 3 社が全株を取得
<2006年 3月 30日号掲載記事>
◆日産、保有する日産ディーゼル株式を売却へ。ボルボトラックが筆頭株主へ
<2006年 3月 21日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【アライアンスの類型】
GM がいすゞとの資本提携を解消し、日産ディーゼルも日産との資本提携を縮小してボルボ・トラックとの資本提携に乗り出した。これらに先行して GM は昨年末以来、富士重工やスズキとの資本提携も解消または縮小していることはご承知のとおりである。
業務提携(アライアンス)には、実質的に一方が他方の技術や製品・サービスを購入してくるに過ぎない個別の「売買契約型」のアライアンスと、資本提携を結んで資金、人事、技術・設備、販売チャネル等、企業活動全体で協力関係を結ぶ総合的な「攻守同盟型」のアライアンスがある。
いすゞ(スズキも)と GM との関係、日産ディーゼルと日産との関係は、これまでの「攻守同盟型」のアライアンスが今後は「売買契約型」のアライアンスに移行していくことを意味している点で共通であり、重要である。
今回は、日本人にとって最も身近な国家間の「攻守同盟型」アライアンスである日米同盟と、企業間の「攻守同盟」である資本提携を対比しながら、後者の本質的な課題を考察していくことにしたい。
【日米同盟のアライアンス論的解釈】
日米安全保障条約で結ばれた日米間のアライアンスは、「売買契約型」なのか「攻守同盟型」なのかという識別に関して、「日米同盟」という通称に拘わらず、実質は「売買契約型」であると認識している日本人が多いのではないかと思う。主に次の 3 点に由来する。
(1) 米国には日本を防衛する義務があるが、日本には米国を防衛する義務がなく、片務的である。
(2) 日本は、米軍基地のために広大な不動産を提供し、犯罪人引渡し等で各種の制約を甘受している。
(3) 日本は、米兵一人あたり 1000~ 1500 万円相当*の「思いやり予算」を支給している。
*日本は年間 4~ 6 千億円と言われる在日米軍の維持経費を負担していると言われ、これを在日米軍の兵員数約 4 万人で割った数字。
つまり、(1)の見返りに(2)と(3)が提供されているという関係にあり、日本は国防業務を米軍にアウトソースしているのであって、日米安保条約とは防衛サービスの購入契約(傭兵契約)だという考え方である。
しかしながら、米国の側から見れば、違った見方になる可能性が高い。
米国は、在外兵力 29 万人のうち十数%に相当する人的資源を日本に投入していることになる。しかも、イラク・アフガニスタンには正規軍だけでは対応できないために、州兵や予備役まで投入せざるを得ないほど人的資源が逼迫する中での話である。
経済的に見ても、米国は国家予算の 2 割弱、年間約 50 兆円以上を国防費に費やしている。それに比較して「思いやり予算」は約 1 %に過ぎない。
つまり、言い方は悪いが、売買契約に基づく日本に対する防衛請負サービスは、殆どフィージビリティの見出せない事業なのである。米国という企業の経営陣(ホワイトハウス、国防・外交当局)がどう考えているかは別として、約2 億人の個人株主(納税者、有権者)たちの眼にはそう映るはずである。
従って、「日米同盟」とは、少なくとも米国側では「売買契約型」のアライアンスではなく、何がしかの事業目的を効果的に達成するための効率的な投資であり、文字通り「攻守同盟型」のアライアンスであると経営者は説明し、投資家の理解を得ていると考えるべきであろう。
【富士重工にとっての攻守同盟型アライアンスの意義】
ここで、先週本誌で本條が触れたトヨタと富士重工のアライアンスを、上記で述べたような日米同盟論を基軸に復習してみることにしよう。トヨタを米国、富士重工を日本と置き換えてみると分かりやすいのではないかと思う。
このアライアンスから富士重工側で期待できる効果として本條は主として以下 3 点を指摘している。
第一に、業績悪化の主因と言われる米国事業でカムリの生産(年産 10 万台)を 2007年から受託することになり、稼働率が向上して固定費負担が軽減される。
第二に、ハイブリッド技術の供与を受け、環境ニーズへの対応を前倒しでき、開発費負担も軽減される。
第三に、ハイブリッドや二次電池の開発のために投じていた工数や設備を本業に回すことができ、競争力や開発リードタイムが向上する。
こうした効果は、日本が日米同盟を通じて享受してきた利益に似ている。
第一に、1950年に勃発した朝鮮戦争により米軍が軍需物資を日本に大量に生産委託したことで、労使対立とドッジ・ラインに伴うデフレに喘いでいた日本の産業経済が復活した。自動車産業も例外ではない。経営危機に陥っていたトヨタがトラックの大量受注で息を吹き返し、初の国産乗用車クラウンの開発プロジェクトを維持できたのである。
第二に、米国からイージス・システムやパトリオット・システムの供与を受け、独自開発するよりも遥かに早く、安く、世界最高水準の防衛技術を手にすることができた。
第三に、兵器・戦術開発(R&D)や軍備(設備投資)への投資を GDP の 1 %(世界水準の 3分の 1)、国家予算の 5 % (世界水準の 3分の 1)に抑えて、その分を社会保障、公共事業、教育、科学技術、経済協力など国民の豊かさや国際社会の中での影響力の向上に使うことができた。
つまり、日本は基地と予算を、富士重工は開発リソースと株式を提供して「攻守同盟型」のアライアンスを結ぶことで、いずれも「売買契約型」アライアンスの効果を享受できるという点で共通しているのである。
【トヨタにとっての攻守同盟型アライアンスの意義】
だが、日米同盟を米国の株主の立場から見てみると、「売買契約型」のアライアンスにフィージビリティが見出しにくいのと同様に、トヨタ・富士重工間のアライアンスもトヨタの株主の立場から見てみると、単なる「売買契約型」のアライアンスとしては割に合わないと映るのではないだろうか。
本誌で本條は、トヨタが享受できるアライアンスのメリットとして、直接間接に以下の 5 点を指摘している。
(1) 自社に不足している開発リソースの確保
(2) (カムリの)現地生産加速による政治的逆風の回避
(3) 空いた国内の生産能力を利用した環境戦略車の増産
(4) 富士重工のブランドや営業力を活用した環境技術のデファクト化や投資回収
(5) 富士重工が持つ二次電池技術の吸収
このうち、第 1 点(開発委託の効果)についていえば、トヨタはグループ内にダイハツ、日野、トヨタ車体、関東自動車などいくつも開発委託先を抱えているし、世界には AVL、MTS、Ricardo など独立系のエンジニアリング会社も多い。資本提携までして富士重工に委託しなければならない絶対的な理由は見出しにくい。
第 2 点・第 3 点(米国での生産委託の効果)や第 4 点(ハイブリッド技術供与の効果)は、それ自体を単独の経済行為として捉えることが可能であり、必ずしも資本提携を必要としない。トヨタの海外生産拠点にはケニアやバングラデシュなど資本関係のない現地企業に組立を委託している実例があるし、フォードや日産にハイブリッド・システムを供与するにあたって両社に出資したわけでもない。
第 5 点(二次電池技術の吸収効果)に関しては、トヨタはパナソニック EVエナジーを通じて自らリチウムイオン電池の技術開発に着手しているし、仮に富士重工の技術が魅力的なものだったとしても(クロス)ライセンス契約で十分である。資本提携が必ずしも必要だったとはいえない。
つまり、上記 5 点は、いずれも一方が他方に対価を支払う形での「売買契約型」のアライアンスの目的・効果としては十分ながら、資本提携をも伴う「攻守同盟型」のアライアンスの目的・効果としては不十分と言わざるを得ない。
日米同盟における米国の立場のような「攻守同盟」を結んでこそ初めてトヨタが獲得できる「何か」の目的・効果の説明が欠けており、それがなければトヨタの株主の納得は得られないのではないかと考える。
【攻守同盟型アライアンスの本質的意義】
そこで、再び日米同盟に戻り、米国にとっての日米同盟の意義を再考してみることにしたい。
ここで世界を、米国的価値観の浸透度(グローバライゼーションの進展度)と、地域の魅力度(市場・資源供給元としてのポテンシャル)、という二つの軸で 4 象限の PPM (プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス)に表すとしたら、次のように分類されるのではないだろうか。
第 1 象限(地域の魅力度は高いが、グローバル化が浸透していない)には、資源が豊富な中東やアフリカが入り、PPM分類では「問題児」に相当するだろう。
第 2 象限(地域の魅力度は高く、グローバル化も進んでいる)には、母国とその周辺の北中南米と、元々市場ポテンシャルが高かった上に近年グローバル化が進んで第 1 象限から移行した中国やインド、東南アジアなどが入るはずで、PPM分類では「花形」に位置付けられよう。
第 3 象限(グローバル化は進んでいるが、地域としての魅力度は低い)には、市場の成熟した日本、欧州、豪州などが入り、PPM分類では「金のなる木」と識別されるだろう。
第 4 象限(グローバル化も進んでおらず、地域としての魅力度も低い)には、米国が敵視政策を取る国々が該当し、PPM分類では「負け犬」に分類と含まれるのではないかと思われる。
この中で、米国が直接的な関心を持ち、主戦場と位置付けるのはどの象限かといえば、第 1 象限の「問題児」と第 2 象限の「花形」になるというのが PPMのセオリーである。
このうち第 2 象現の「花形」はグローバル化の枠組みには入ってきているので軍事的アプローチよりも外交・経済政策がより効率的で有効な手段となりうる。
一方、第 1 象限の「問題児」に対しては時として軍事的メソッドを使ってでも米国的価値観の枠組みに入れ込もうとする動機付けが働きやすいことになる。
いずれも地域としての魅力度が高い分だけリソースの投入が必要となるので、それを別の象限から捻出してこなければならない。そこで注目されるのが第 3象限の「金のなる木」である。ここではできるだけ手を掛けずに維持的な投資だけを継続して効率性と現状維持を図ること、そしてそこから得られた収穫を第1象限や第 2 象限に回すことが課題になる(ついでに言えば、第 4 象限の「負け犬」では早期の撤退・清算が課題)。
つまり、世界唯一のスーパー・パワーとなった米国は一ヶ国で全世界と同時に対峙しなければならなくなったが、さすがに全世界に対して均一の注力度で対応することは不可能だし、効率が悪いので、メリハリを付けた重点管理が必要となり、第 3 象限の「金のなる木」はいわば子会社に任せて効率性と現状維持に移行したと考えることができる。
効率性と並んで現状維持が重要だというのは、米国が第 1 象限の「問題児」との戦いに集中している間に第 2 象限の「花形」や第 4 象限の「負け犬」が予想外に台頭して米国の利益やポジショニングを損なうことは避けたく、勢力図の固定化が望ましいという意味である。
日米同盟という「攻守同盟型」のアライアンスを通じて、米国が日本に期待する役割、投資家に対して説明しているアライアンスの目的や効果はそこにあり、フォーカス・セグメント以外での米国の競争相手の行動を監視し、牽制し、状況によっては応戦し、撃退する役割を日本が果たしてくれるならば安い維持的投資だと考えられているのではないだろうか。
【企業間の攻守同盟型アライアンス】
同じことは、企業間の攻守同盟型アライアンスである資本提携にも当てはまるのではないかと考えられる。
今や世界の自動車産業のトップ・ランナーとして世界市場と対峙することになったトヨタも、米国と同様に PPM に基づく重点管理を迫られていると考えられる。
トヨタにとっての第 1 象限は、地域軸としては中印露などの新興国であり、商品面では高級セダン(レクサス)・大型トラック(北米用)・小型エコノミーカー(新興国用)セグメントであり、技術面ではハイブリッド・燃料電池等の非内燃機関系の動力システムであろうと考えられる。
第 1 象限での戦いを後顧の憂いなく展開するためには、日米欧市場やクロスオーバー・スポーツカーなどのニッチセグメント、既存の機関・駆動システムで、他社が予想外に伸張し、取りこぼしが発生することは極力避けたいはずである。
先進国に強く、ニッチ・セグメントと既存の機関・駆動系システムで独自のポジションを築いている富士重工に対して、そうした主戦場以外での監視・牽制と状況によっては応戦・撃退を期待しているとしたら、それは「攻守同盟型」のアライアンスとなる。単なる「売買契約型」のアライアンスでは手にすることができない戦略的な必要性・合理性があると考えられる。
このように考えてくると、いすゞと GM の関係、日産ディーゼルと日産とのアライアンス関係は、資本提携を伴う「攻守同盟型」のアライアンスの形式を取っていたものの、GM や日産の役割や責任を一部肩代わりして彼らの競争相手の伸長を防いだり、叩いたりするような「攻守同盟型」の要素は殆ど持っておらず、実質的には「売買契約型」のアライアンスに終始したのではないかと思われる。
そういう意味では、最近の一連の出来事は(直接的には GM や日産固有の事情がトリガーになっているとはいえ)本質的には形式と実質の捻れを解消する動きだったと考えることができる。
また、今後、自動車業界では業界の再編・統合の動きが再燃してくる可能性があるが、その際に資本提携を伴うとすれば、それが単に「売買契約型」のアライアンスとしての条件を満たしていることだけでなく、「攻守同盟型」のアライアンスとしての条件を満たしたものになっているかどうかは注目すべきポイントだと考える。
<加藤 真一>