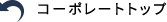自動車業界ライブラリ > コラム > 今更聞けない財務用語シリーズ(4)『MBO』
今更聞けない財務用語シリーズ(4)『MBO』
日頃、新聞、雑誌、TV等で見かける財務用語の中でも、自動車業界にも関係が深いものを取り上げ、わかりやすく説明を行っていくコラムです。
第4回の今回は、MBOについてです。
第4回 『MBO』
——————————————————————————–
前回のTOBの解説の中でMBOについて若干触れたので今回はMBOについて解説したい。
MBOは「Management Buy Out」の略であり、企業の子会社や事業部門の経営者等がベンチャーキャピタルや投資ファンド、金融機関から資金を調達し、その子会社の株式を買収したり、新会社を設立し、営業資産を譲受する形態の企業買収の手法のことを言い、別名「現代版暖簾分け」とも言う。
自動車業界では、キリウ、リズムなどが日産の傘下から独立した際にこの手法を用いており、最近ではマツダレンタカーがこの手法でマツダから独立している。
MBOは、企業の後継者に悩んだオーナー株主が自社株式の売却する手法とし英国で生まれたと言われている。日本ではバブル経済が崩壊し、企業の間で事業の選択と集中の機運が高まった 1990年代後半から実例が増え、これに呼応するように支援する投資ファンドの設立も相次いでいる。2003年 11月にはみずほフィナンシャルグループはMBO専門の第2号ファンドを設立している等、今後も日本においてMBOが活発になると予測されている。
主にMBOはオーナー株主が後継者に悩み、現経営陣に事業を承継する場合と親会社の業績が落ち込み、事業の選択と集中を進める中で子会社を経営陣に売却する場合に行われる。通常、経営陣が株式を買い取る際に全額負担することができない為、投資ファンド等が経営陣と一緒に出資するケースが多い。出資後は、ファンドは企業の経営革新を進め、価値増大を図った上で当該株式を売却することでキャピタルゲインを得ることを目的としており、経営陣もストックオプション制度などの導入により成功報酬を得ることが可能となる。
敵対的買収などと比べた場合の、MBOのメリットとしては当該事業を熟知した経営陣によって運営されること、経営方針の大幅な変更が無く従業員の雇用が維持できること等が挙げられる。
メリットを活かした形での成功例を見てみよう。
あるAという自動車メーカーがB社という部品メーカーを子会社として保有していたが、A社は業績が悪化した為、金融機関主導で事業再生することとなり、B社は売却候補となった。
A社にとってB社は重要な部品のサプライヤーである為、できればその部品の事を熟知し、経営手腕に長けている人間に経営をして欲しいと考えており、その要件をB社の経営陣は満たしている。
同様にB社の経営陣もまだ顔の見えない第3者に売却されるのであれば、独立したいと考えていた。但し、B社の売却価額は高額であり、経営陣の手許にある預金だけでは、買収は不可能であった。
一方、Cファンドというファンドも自動車業界に興味があり、業界動向をチェックしており、B社の扱っている部品の優位性や経営陣の経営手法を高く評価していた。そこで、Cファンドは経営陣でB社株式の5%を保有し、残りの95 %を自ら出資するスキームを提案、A社はそのスキームを了承し、MBOを行い、B社は独立系のサプライヤーとなった。
その後、B社の業績は堅調に推移し、A社以外の自動車メーカーにも部品を納入するなど販路も拡大できたので上場することができた。Cファンドも上場に合わせ、株式を売却し、キャピタルゲインを得ることができた。この時、経営陣も保有していたストックオプションも上場に合わせ売却することができ、報酬を得ることができた。
上記は成功例だが、MBOは親会社等からの独立を意味することから親会社の傘下で得られた人的な面や財務的な面での支援を享受できなくなる点に留意する必要がある。
失敗例としてはMBOしたもののA社の業績不振の煽りを受け、B社の業績も落ち込み、ファンドは投資採算が取れないまま、第3社に売却し、その時点で現経営陣も解雇されてしまう、という最悪のケースも考えられる。
子会社の経営陣には親会社との良好な関係を維持しつつも、親会社のみに依存した取引形態から脱却し、独自の取引を開拓し、借入先の金融機関と関係を築き、従業員の教育を行うなどの経営手腕が求められるのだ。MBOに成功すれば多額の報酬を得られる可能性もあるが、失敗した場合には解雇されたり、株主としての責任を追及されるリスクも伴う。このようにMBOとは特に子会社の経営陣にとってハイリスクハイリターンな手法と言えるだろう。
経営陣はMBOを希望するのであれば、個別のケースにもよるが、自社の製品やサービスの優位性や業界内でのポジション、業界再編などの動向を確認し、経営方針を明確にした上で、MBO後に独立した事業運営をしていけるかどうかの見極めを行なうことが必要となるだろう。
<篠崎 暁>