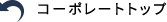自動車業界ライブラリ > コラム > M&A と研究開発効率向上戦略の考察
M&A と研究開発効率向上戦略の考察
◆ユーシン、旧リップルウッドの主導でナイルスを買収へ
<2007年03月12日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【はじめに】
日経朝刊は、投資ファンド RHJ インターナショナルが筆頭株主として 20 %を出資する旧マツダ系自動車メカトロニクス部品大手のユーシンが、同業で同投資ファンドの 98 % 子会社である旧日産系のナイルスを買収する方針であると報じた。
ユーシン側は本件決定事項ではないとしながら、選択肢の一つとして本件を検討していることは声明で認めている。
記事によれば、調達の一本化や生産拠点の統廃合によるコストの削減と、製品群の拡充、研究開発効率の効率化が買収の目的・効果だという。いわゆるシナジー効果であるが、コスト・シナジーの方は比較的理解し易い。では、製品群の拡充や研究開発効率向上といったアップサイドのシナジーはどのようなものか分かりにくいところがある。本誌読者の大半が研究開発部門に所属することを踏まえて、今回は M&A と研究開発効率の関係性・意味合いを考察してみたい。
【研究開発部門統合の意味】
以下のモデルケースによれば、技術ストックが重複する同業者間の M&A においては、技術開発の重複を減らして製品化率を向上させながら、製品開発エンジニアの数を増やすことによって製品開発件数を増やして売上を成長させることが可能で、それこそが M&A の究極の意義・目標であることが分かる。
記事の2社よりは遥かに小さな部品メーカー 2 社をモデルケースとして仮定する。技術開発 10 名、製品開発 50 名、総勢 60 名のエンジニアを抱える A社と、技術開発 15 名、製品開発 75 名、総勢 90 名を抱える B 社である。
A 社も B 社も現状、次の前提条件で事業を行なっている。
・エンジニアの人件費は一人あたり年間 5 百万円。
・技術開発エンジニアは、一人あたり年間 5 件の技術開発を行なう。
・技術開発成果は全て 10年間技術ストックに蓄積され、順次製品開発に活用されていく。
・年間の製品開発件数は、技術ストックの 2 % (ストック 100 件に対して毎年 2 件の製品化率)。
・開発された製品は 5年間(製品寿命)にわたり、各々年間 6 百万円の売上をもたらす。
・技術ストックは社内的には全く重複しないが、2 社間では完全に重複している(つまり、A 社は同社が製品化するのに必要な技術を漏れなくダブりなくストックしているが、B 社の技術ストックがあれば全て製品化が可能)
・製品開発エンジニアの生産性は最適化されており、現状では改善が期待できない(つまり、技術ストックが増えても製品開発エンジニアの数が増えない限り製品開発件数は増えない)。
・売上に上方硬直性はない(つまり、製品化できた分だけ売上が伸びる)。
・研究開発費の内訳は全てが人件費で、またそれが全社の原価・費用の全てである(つまり、売上高から研究開発費を差し引いた残りが各社の利益)。
<モデル分析>
モデルケースでは、A 社・ B 社とも全く利益も損失も出ない。
上記前提条件に基づく A 社、B 社の開発能力は次の通りとなる。
・エンジニア総数: A 社 60 人(技術開発 10 人+製品開発 50 人)+B 社90 人(技術開発 15 人+製品開発 75 人)=合計 150 人(技術開発 25 人+製品開発 125 人)
・技術ストック: A 社 500 件+B 社 750 件=合計 1,250 件
・製品開発件数: A 社 10 件+B 社 15 件=合計 25 件
・製品化率: いずれも 2 %(前提条件の通り)
・製品開発生産性: 製品開発件数÷製品開発エンジニア数=いずれも製品開発エンジニア一人あたり年間 0.2 件(違う言い方をすると製品開発 1 件あたり 60 人・月)
また、A 社、B 社の損益は次の通りとなる。
・売上高: A 社 300 百万円+B 社 450 百万円=合計 750 百万円
・研究開発費: A 社 300 百万円+B 社 450 百万円=合計 750 百万円
・利益: A 社 300-300=0 B 社 450-450=0 合計 750-750=0
・R&D 比率: A 社 300÷300=100 % B 社 450÷450=100 % 合計 750÷750=100 %
<縮小均衡によるコスト・シナジー分析>
M&A によって真っ先に検討されるのが重複の無駄の排除である。このケースでは技術開発・技術ストックが 2 社間で完全に重複しているのでその無駄を省くことになる。
両社合わせて現状 25 名の技術開発エンジニアがいるが、これを 15 名に減らしても製品開発エンジニア数が同じならば理論的には従来どおり年間 25 件の製品開発が可能になるから、2社合わせた開発能力は次の通りで、製品化率が向上する。
・エンジニア総数: 140 人(技術開発 15 人+製品開発 125 人。従来比 10 人減)
・技術ストック: 750 件(B 社の技術ストック)
・製品開発件数: 25 件(従来どおり)
・製品化率: 25÷750=3.33 %(従来の 1.67 倍に向上)
・製品開発生産性: 一人あたり年間 0.2 件(← 25÷125 人) or 60 人・月/件
また、A 社、B 社合わせた損益は次の通りで、研究開発費の削減分が増益となる。
・売上高: 750 百万円(従来どおり)
・研究開発費: 700 百万円(←@5 百万円X 140 人)
・利益: 750-700=50 百万円(コスト・シナジー)
・R&D 比率: 700÷750=93 %
<拡大均衡によるフル・シナジー分析>
縮小均衡によるコスト・シナジーでは製品化率は向上しても製品開発件数自体は増えない。従って売上高も増えず、企業としての成長が望めない。さらに数値には表れないが、実際には技術開発エンジニア削減による全体の士気低下の影響も計り知れない。
これに対して、エンジニア数は減らさずに(従って士気を落とさずに)製品化率の向上によって製品開発件数の向上をも狙うのが拡大均衡によるフル・シナジーである。
技術開発エンジニアを元の 25 人に戻すが、復活分は新製品の開発に有用な技術開発に投入し、コスト・シナジーの成果として向上した製品化率は下げないようにする。技術開発ストックは従来どおりの水準を回復するから、製品化率が向上した分だけ製品開発件数・売上高が増加し、企業が成長する。
・エンジニア総数: 150 人(技術開発 25 人+製品開発 125 人)
・技術ストック: 1,250 件 (← 25 人×5 件/年×10年)
・製品開発件数: 41.7 件(技術ストックX製品化率)
・製品化率: 3.33 % (コスト・シナジーと同一)
・製品開発生産性: 一人あたり年間 0.33 件(製品開発件数÷製品開発エンジニア数)または 36 人・月/件
また、A 社、B 社合わせた損益は次の通りで、売上高の増大により大幅な増益が見込まれる。
・売上高: 1,250 百万円 ← 41.7 件/年×6 百万円/件×5年
・研究開発費: 750 百万円 (従来どおり)
・利益: 1,250-750=500 百万円(フル・シナジー)
・R&D 比率: 750÷1,250=60 %
<制約を加味したリアル・シナジー分析>
拡大均衡によるフル・シナジーには重大な欠陥がある。製品開発エンジニアの生産性は既に最適化されているという前提にも拘らず、技術開発ストックの増加分だけ製品開発件数が増加するとしていた点である。
そこで、製品開発生産性を従来どおり一人年間 0.2 件に戻すとともに、技術開発ストックおよび製品開発件数の増加分に見合うだけ製品開発エンジニアの数を増やしたものがリアル・シナジーである。文字通り現実的な企業の成長シナリオと考えられる。
・エンジニア総数: 233 人(技術開発 25 人+製品開発 208 人←製品開発件数÷生産性)
・技術ストック: 1,250 件
・製品開発件数: 41.7 件(技術ストック×製品化率)
・製品化率: 3.33 %
・製品開発生産性: 一人あたり年間 0.2 件(従来どおり)
・売上高: 1,250 百万円
・研究開発費: 1,167 百万円(←@5 百万円×233 人)
・利益: 83 百万円(リアル・シナジー)
・R&D 比率: 1,167÷1,250=93 %
【研究開発部門のM&Aへの備え】
ここまで見てきたのは、経営者から見た場合の研究開発部門統合の意義だったが、研究開発部門の側は M&A をどう捉えてどう備えるべきだろうか。
その前に上記スタディについて補足しておかなければならない。
上記は A 社・ B 社が現状ブレークイーブンであるという前提でのスタディであるが、異なる前提条件を置いて同じスタディをやり直してみると、次のことが言えるのである。
・A 社・ B 社が現状赤字の場合には、最良の選択肢は縮小均衡型の統合である。
・A 社・ B 社が現状黒字の場合には、必ずしも統合がベストの選択肢とは言え
ず、各社単独でエンジニアを増やして成長を目指す方が理にかなう場合もある。
・しかし、それは概ね単独で 2 倍以上に事業拡大できる場合であって、そうでなければ拡大均衡型の統合の方が効果が大きい。
つまり、経営者が同業種間の M&A に踏み切る判断をするのは、赤字の縮小均衡を目指す場合か、そうでなければ単独で可能なスピードよりも早く製品開発を進めなければならないという動機付けが強く働いているケースのどちらかである。(異業種との統合の場合は事情が異なる。モジュール提案力を高めるための範囲の経済を追求するもので、成型用樹脂素材メーカーの住友ベークライトがベルギーのガラス繊維メーカーを買収したケースはそれにあたる。)
後者のケースの代表例は、2006年 1月に光洋精工と豊田工機が合併して成立したジェイテクトであろう。また、ボルボ・トラックによる日産ディーゼル工業の完全子会社化も同じ文脈で認識できる(両社とも大型中心の製品構成で、開発課題も環境対策で共通している同業者である)。安全性と環境性に関わる自動車メーカーの開発課題に対応するために電子制御によるエンジン・駆動・伝達・操縦系部品、さらにはそれらの部品の動作に必要な検知・演算・操作・表示系の関連電子製品の需要が急拡大しているから、そうした製品のメーカーには開発スピードを高めるための企業統合が共通の検討課題になっていると考えておくべきであろう。自社においてもいつでもありうることだと認識しておくべきである。
また、研究開発部門の統合を必ずしも否定的に捉えるべきではないだろう。
上記に見てきたとおり、赤字会社の場合でない限り、M&A に伴って研究開発部門を縮小することは経営的に得策とは言えず、寧ろ強化する方向性の動機付けが働くからだ。更に開発スピードを加速するための設備投資が促される可能性もあるし、従来ならば既存の枠組みに囚われて取り組むことが認められなかった新たな開発テーマが解禁される可能性もある。
それでも、どうしても研究開発部門の統合を避けたいのであれば、M&A に先んじて製品化率や製品開発生産性の制約条件になっているものを自ら発見・定義し、その解決策を打ち出して開発スピードを加速する必要があるだろう。
<加藤 真一>