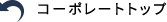自動車業界ライブラリ > コラム > 自動車産業界における新たな産官学連携体制に向ける期待
自動車産業界における新たな産官学連携体制に向ける期待
今回は「自動車産業界における新たな産官学連携体制に向ける期待」という
テーマでご協力をお願いしたアンケート結果を踏まえたレポートです。
https://www.sc-abeam.com/sc/?p=7297
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【はじめに】
昨年来、自動車産業(部材等周辺産業を含む)において、新たな産官学連携
体制の構築が進んでいる。例えば、近年、以下の様な団体が発足した。
○ 新構造材料技術研究組合(ISMA): 軽量化(半減)関連技術の共同研究
を目的に2013年10月に発足。素材・自動車メーカー、産総研、名大、等が参加。
○ 自動車用内燃機関研究組合(AICE): 内燃機関の性能向上技術の基礎・
応用研究の為、2014年4月に発足。自動車メーカー9社、及び日本自動車研究所、
産総研が参加。
なお、これら動きと前後するが、経済産業省は昨年11月に発表した「自動車
産業戦略2014」中、「研究・開発・人材戦略」にて「より戦略的な選択と集中
による経営資源の配分や開発・生産体制の必要性」を唱え、内燃機関、電池
(燃料電池を含む)、材料(軽量化等)、モーター・パワエレ、自動運転、生
産技術を重点6分野(第一弾)と定め、これらについて、「研究開発の視点の
みならず、国際標準化を活用した技術の実用化・普及といったビジネス視点に
おける協調も検討を行い、その為の新たなプラットフォームを検討する」とし
ている。
更には、日本政府の国家プロジェクトとして、昨年5月に「SIP: 戦略的イ
ノベーション創造プログラム」が本格始動、「世界で最もイノベーションに適
した国づくり」というスローガンの下、10 のプロジェクトが展開されている。
その中には、「革新的燃料技術」、「自動走行システム」という自動車に直接
関係あるプロジェクトも含まれており、夫々で、産官学連携体制を組みつつ、
先述の研究組合とも連携しつつ活動が推進されている。
斯様に、我が国における産官学連携は、今日、自動車産業においても、嘗て
ない程の盛り上がりを見せていると言える。
本稿では、これら同時多発的に興った個々の活動詳細に踏み込むのではなく、
寧ろ、その背景要因や、今後の動向、課題について、先般のワンクリック・ア
ンケートの結果や、読者皆様からのご意見を踏まえて、マクロ的に考察してみ
たい。
【ワンクリック・アンケートの結果】
まず、ご回答を頂いた読者各位には深く感謝の意を表したい。
ワンクリック・アンケートの結果は次の通り。
1. 産官学連携活動により、産業界に協調の土壌が齎され、技術開発の効率化
が進む 33 %
2. 産官学連携活動により、対象となる技術の国際的標準化が進み、実用化・
普及が進む 19 %
3. 産官学連携活動により、学術界と産業界の夫々が持つ異質の「知」が融合
することで、斬新なイノベーション(新技術・新産業等の創出)が齎される
21 %
4. 産官学連携活動により、産業界、学界にとって上記以外の新たな恩恵が齎
される 7 %
5. 産官学連携活動が生み出す恩恵には余り期待していない(本件に余り関心
ない、を含む) 20 %
また、読者の皆様から頂いたコメントの中で代表的なものを御紹介すると次
の通り。
○「次世代自動車の開発が産学共同で行われている。共同により効率的な作業
が可能になる。産と学の役割分担は今後より進むだろう」
○「弱みとなっている次世代基礎研究分野における産官学連携の恩恵が得られ
る事を期待したい」
○「(ドイツなどとの比較で)日本でもより大規模な組織化や資金の準備が進
めば、大きな成果が期待できると思う」
○「自動車各社が持っているコア技術を何処までオープンにするかが課題。寧
ろ、共同研究する大学・研究室のレベルアップなどが期待できるのでは」
○「産官学連携の成功事例を見たことがない」
○「防衛産業ならまだしも、民需に関しては今更感を否めず」
産官学連携へ期待するの声が総じて多数だが、反対意見も可也ある。
【産官学の半世紀を振り返る】
産官学連携活動の歴史は日本の近代化にまで遡る。然し、過去半世紀に絞っ
て考えると、その底流が俯瞰できる。
1980年代、自動車をはじめ高度成長期を経た日本企業の米国進出が最頂期を
迎える中、米国は、日本の官民協力を参考にしつつ、対抗措置として高度知識
基盤社会に合致した産業の創出を図るべく産官学連携推進に向けての各種施策
を推進した。①大学の研究成果の特許化、②特許の企業への移転、③大学発ベ
ンチャー企業の育成、が活発に行われ、大学がイノベーションの源泉の役割を
果たし、IT、バイオなど成長性の高い分野を中心に大学発ベンチャー企業が生
まれた。その興隆が、1980年代から続いた米国経済低迷からの脱却と活性化に
大きく貢献したといわれている。
一方で、日本は、1990年代初めのバブル崩壊以降、経済復興が遅れる中、米
国再生の秘訣を「大学を中心とする先端研究組織からの知識のシーズの活用」
にありと考え、積極的に米国の政策を踏襲しようとした。1998年に「大学等技
術移転法(承認TLO)」により、産業活性化・学術進展のため、大学の技術や
研究成果を民間企業へ移転する仲介役となる承認TLO(技術移転機関)の仕組
みを制定した。1999年には「産業活力再生特別措置法(日本版バイ・ドール
法)」により大学で生まれた発明を特許で守る仕組みも整備した。更に、2000
年の産業技術力強化法により国立大学教官の兼業要件を緩和した。また、2003
年からは、大学知的財産本部整備事業が展開され、翌年からは国立大学法人化
が順次実施された。そして、2008年には、文部科学省が産官学連携戦略展開事
業を開始し、産学連携の基盤が強化された。
然しながら、日本では、産官学連携は目した程の成果には至らなかった。次
世代新産業の創造では米国に遠く及ばず、2001年の「大学発1000社構想」は、
数の追求に終始するあまり、中身の成功に乏しい結果に終わり、加えて、2010
年からの「事業仕分け」によりそれ迄の種々創生事業が悉く廃止の憂き目に直
面した。こうした過去を見ると、読者からの否定的な見解にもとくと頷ける。
【激変する環境】
然し、それでも科学は進歩し時代は流れる。リーマンショック以降、日本の
産業界の一翼を担った電機、家電、半導体等の産業は言語を絶する厳しい状況
を迎えた。一方、自動車産業は、未だ日本にとって「国民産業」と誇れる存在
ではあるものの、取り巻く環境は厳しく決して油断することは出来ない。2000
年を境に世の中は所謂「オープン・イノベーション」の時代に突入した。
そもそも、「オープン・イノベーション」の手法とは、「摺り合わせ」・
「自前主義」を基調とする従来の「自動車産業的手法」とは相いれ難い。然し、
クルマのパワートレインが多様化し、続々と安全技術が投入され、通信機能が
高度化し、技術開発課題がこれまでとは比較にならない程膨れ上がっている。
ならば、より、自動車産業全体としての在り方を見直し、より、マクロ効率を
追求した形に改革すべし、というのが先述の「自動車産業戦略2014」における
「研究・開発・人材戦略」の主張だ。
一寸脱線するが、一頃、「クルマのIT化」と言われたが、最近では、「クル
マのIoT(Internet of Things)化」とも言われる。つまり、モノとしてのク
ルマが大きく変化している。それと共に、その開発手法・要件も大きくIT化、
IoT化する中にあって、旧来型産業であった自動車産業は、今や次世代型産業
へと「転生」したとも捉えられないだろうか。もし、そうであるなら、産官学
連携が自動車をその手法の対象とし、中心的なテーマに位置付けることは何ら
不自然なことではないだろう。
【イノベーション・ナショナル・システム】
日本経済を再生させ、日本を元気にするために「科学技術イノベーション」
に期待が集まる。その実現に向け、「我が国のイノベーション・ナショナル・
システム改革戦略」が、急ピッチで推進されている。日本にとっての「お手本」
は米国だけではない。ドイツにも熱い視線が向いている。
ドイツの公的研究機関「フラウン・ホーファー研究所」がその一つだ。同所
は、産業に直接役立ち、総じて広く社会の利益になる応用研究を行うことを使
命とし、その為の研究資金を「政府拠出金」「公的プロジェクト」「産業から
の受託」夫々から1/3毎調達することを自らの特徴としている。適度な受託研
究を実施することで「産」との距離を的確に保つことがその狙いだ。
このモデルに倣ってか、昨年6月に決定された「日本再興戦略」の中、日本
でも公的研究機関のあり方が見直されている。そこでは、「産」からの受託研
究に力点を置き、基礎研究に強い「学」、と応用研究を得意とする「産」、そ
の両者の「橋渡し」の役割が「官」に求められている。
例えば、産業技術総合研究所(産総研)は本年度より新たに国立研究開発法
人に指定されると共に、その研究成果の産業界への「橋渡し」機能を強化し、
事業化に取り組み、社会に還元する方針を改めて表明した。組織も改編し、企
業からの受託研究を原則化し、その為のマーケティング機能も強化する方針を
打ち出している。そして、新たな取組の一つとして、「自動車ヒューマンファ
クター研究センター」を新たに開設した。そこでは「安全で楽しい運転の実現
に向けて、ドライバーとしての人間の特性を研究すること」がテーマとして掲
げられている。
【結論】
これら自動車産業を舞台とする産官学連携の新たな取組が成功し、成果が生
まれることは、日本の自動車産業そのものの強化に直接繋がることだ。繰り返
しになるが、日本の産業復興の長年のテーマで、産官学連携が目標とした「次
世代産業の創成」の真ん中にいつしか自動車産業は位置付けられた。これを
「千載一遇のチャンス」と見るか、「背水の陣」と見るか、何れにしても答え
は「後戻りしない」ということではないだろうか。
2000年頃、自動車産業が大きな変革を迎える中、「系列解体」とよく言われ
た。事実、自動車サプライチェーンにおける資本関係のあり方は可也適正化さ
れた。気のせいか、「系列」という表現も今日では余り耳にしなくなった様に
思える。然し、「産業システムのあり方」「技術開発のあり方」に適いつつ、
多少は変貌しながらも、各自動車メーカーを頂点とする企業グループは未だ存
在する。勿論、その存在そのもの自体の是非を問う積りはない。然し、その存
在理由となる「システム」自体が、今、変わりつつあるのではなかろうか。
本稿に於いては、その変化を産官学の新たな取組みという観点から観察した。
然し「変化」はそれだけではない。クルマの設計思想そのものが「アーキテク
チャー」重視に変貌したこと、そこで、「設計起点のモジュール化」が生まれ、
自動車業界に浸透しつつある。、更に、このモジュールが自動車メーカー間で
もそのうち共有される様になると言われる。ここでも、流れは「クローズド」
から「オープン」に向かっている。
ならば、「オープン」を前提として、自社の技術戦略を練り直すべきではな
かろうか。外から自社に調達すべきは何か、自社から外に出すべきは何か、外
に出すことによって技術はまた別の用途と結びついたり、他の技術と結合する
機会に恵まれる。自社の技術ポートフォリオ戦略をそうした「オープン」な体
系で見直す、斯様な「場」としての産官学連携体制を、そのメンバーでもある
「産」として積極活用し、単なるマクロ効率化だけでなく、より積極的な知の
融合が齎すイノベーションの場へと積極的に昇華してくべき時代が今、始まろ
うとしている、と筆者は考えている。
<大森 真也>