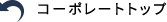自動車業界ライブラリ > コラム > ディーラーの行方(4)
ディーラーの行方(4)
弊社親会社であるアビームコンサルティング(旧デロイトトーマツコンサルティング)が、自動車業界におけるモノづくりから実際のチャネル戦略に至るまで、さまざまな角度から提案していく。
アビームコンサルティング ウェブサイト
http://www.abeam.com/jp/
第 4 弾は、弊社副社長の長谷川博史が、ディーラーの現状、今後について 5 週に渡って紹介する。今回はその第 4 回にあたる。
第4弾『ディーラーの行方(4)バランスシート調整の施策』
(日刊工業新聞 2004年08月25日掲載記事)
——————————————————————————–
【前回までの纏め】
前回までは如何にしてディーラーの売上を増加させるかという観点から、「新車販売」というプラットフォームと、その上に積み上げる、所謂「周辺ビジネス」(アプリケーション)の 2 つの領域における「収益向上の為の施策」を述べてきた。即ち、会計的に言えば P/L における貸方に相当する。
【今回は】
今回は同じく会計面から見れば、B/S における「借方」に相当する「資産内容の充実や効率化・現金化」、及び「費用削減など」において、既にディーラー各社が手掛けている施策以外を念頭に、幾つかの可能性を提示してみたい。
【ディーラーにとっての支払金利負担】
第 1 回にディーラーの経営状況と題して、社団法人日本自動車販売協会連合会が発表しているディーラー 1 社当りの損益計算書の各勘定が過去 10年でどのように推移してきたかを述べた。その中で最も顕著な差が生じていたのが「支払金利」の項目である(平成 5年:1.6 億円→平成 15年:0.3 億円へと 80 %減)。支払金利は一般的に有利子負債×借入金利(率)で算出されるが、構成要素の片方である有利子負債残高を見ると、この 10年間で 11 %しか減少していない(平成 5年:31 億円→平成 15年:27 億円)。即ち、支払金利の実額が大幅に減少している原因は、もう一つの構成要素である借入金利(率)が超低金利時代突入により大幅に低下したことやメーカーから何らかの低利金融支援が存在したことにあると考えるべきである。
【低金利トレンドは永遠には続かない】
但し、経営者としては今後もこの超低金利時代が永遠に続くと見るべきではないし、またメーカー等からの金融支援も永続ではないだろう。即ち、可能であれば負債を削減しながらも手元にキャッシュを残すといった形でバランスシートを整えないと、このままでは景気の回復に伴い販売は増加(売上高は増加)しても今度は支払金利が増加して、損益的には依然厳しい状況となってしまう可能性がある。
【固定資産に目を付けろ】
そこで目に付くのが、固定資産の金額である。ディーラー 1 社当りの有形固定資産残高は 25 億円と、上述した 1 社当りの有利子負債残高の 27 億円にほぼ一致する。もし、この有形固定資産を何らかの形で流動化して景気回復前に有利子負債の返済に充てることが出来れば、負債の劇的な削減と同時に収益構造の変革を達成することが可能になる。
【不動産投資信託・REITとは】
これを可能にする手法として、筆者は不動産投資信託(REIT)に注目している。日本でも最近総合的な REIT がスタートし、かなりのレベルでオペレーションしているが、米国では不動産の投資対象がより細分化されており、自動車小売拠点のみに特化した形で不動産を取得し、投資対象として市場に提供している会社もある。例えば Capital Automotive 社という会社は、全米 313 の自動車小売拠点(不動産)に 17 億ドルを投資しており、保有資産は全米 30 州にまたがり、43 のブランドをおよそ 436 のフランチャイズでオペレーションしている。(同社ホームページより。)仕組みの概要は簡単で、既存のディーラーオーナーから土地建物を買い上げ、同時に同ディーラーに同じ土地建物を貸し付ける。買い上げのキャッシュは信託を通じて一般の投資家から徴収。投資家は賃料を裏づけにした証券を購入。ディーラーから見ると、自社の土地建物を流動化し相対的に低い割引率で現金化しながら(即ち有利子負債の返済に充てられる)オペレーションが可能。また、リスクマネーは市場を通じて一般の投資家が供給してくれる為、不動産相場やディーラーオペレーション巧緻による業績変動に基づく賃料不払いリスクも、結果的には薄く広く投資家にダイルートされる。
【終わりに】
こういった仕組みは最終的に投資家に証券を販売する必要が生じることから、ある程度の資産規模が纏まらないと実現出来ない。代替投資手段を巧く活用して資本コストを最小化していく為には業界団体やメーカー、若しくは比較的規模の大きなディーラーグループなどがイニシアティブを取っていくことが重要であろう。
<長谷川 博史>