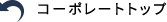自動車業界ライブラリ > コラム > 今更聞けない財務用語シリーズ(1)『持ち株会社とは?』
今更聞けない財務用語シリーズ(1)『持ち株会社とは?』
日頃、新聞、雑誌、TV等で見かける財務用語の中でも、自動車業界にも関係が深いものを取り上げ、わかりやすく説明を行っていくコラムです。
今回は、第1回として、持ち株会社についての説明です。
第1回 『持ち株会社とは?』
——————————————————————————–
最近、経営統合や企業再編のニュースが頻繁に紙面を賑わしている。特に金融機関の買収、統合に関するものは多い。三菱東京フィナンシャルグループとUFJ ホールディングスとの統合や、UFJ カードと日本信販の合併等についての報道は、読者の皆様の記憶にも新しいところであろう。
自動車業界も例外ではなく、近年、日立製作所によるユニシアジェックスの完全子会社化、日産とルノーの提携、ダイムラーとクライスラーの合併など、大型の企業再編の波が着実に押し寄せてきている。
勿論、一口に企業再編・経営統合と言っても、技術提携だけを行うものもあれば、株式の持ち合いを行うケース、合併による完全統合などまであり、提携の度合いによって、その手法も異なる。
昨今の経営統合においては、「持ち株会社化」という手法が検討されるケースが増えてきている。前述の金融業界を見ると、国内大手金融機関ではほとんどの場合で持ち株会社化の手法が導入されている。「○○ホールディングス」といった社名を見かけることが多くなったという読者も多いだろう。
今回は、この「持ち株会社」が何か、どういった場合に有効か、紹介したい。
「持ち株会社」には「事業持ち株会社」と「純粋持ち株会社」との2種類がある。「事業持ち株会社」とは傘下の企業の経営を行いながら独自の事業を行っている会社のことで従来型の持ち株会社の事である。
一方、「純粋持ち株会社」とは、グループ内の企業の株式を保有し、グループ内の経営方針の決定、資金調達など経営管理を行う中核企業の事である。製造販売を行わないので、グループ企業からの配当と金利収入だけが収益となり、経営管理を行う人員の人件費等の管理コストが費用となる。
昨今よく見かける「○○ホールディングス」の大半は、後者の「純粋持ち株会社」であり、通常「持ち株会社」と言えば「純粋持ち株会社」を指す。
純粋持ち株会社は、グループの経営管理に特化することで、事業部門の切り離し、類似事業の統廃合、新規事業への参入といったグループ全体の戦略に注力することを可能とし、機動的な戦略を目指す形態である。
日本における純粋持ち株会社の原形は戦前の財閥にある。ところが、戦後財閥は公正な自由競争の発達を妨げ、全体主義につながるものとして忌避された結果、純粋持ち株会社の形態・手法も長らく禁止されてきた。それが、産業界の求めに応じる形で1997年に解禁、復活したのだ。その後、企業再編税制の整備、商法改正により従来の手続き等が簡便化され、使い勝手が良くなった事から経営統合の手法として定着してきている。
では、なぜ産業界は「純粋持ち株会社」を求めたのであろうか。一言で言えば、経営資源の最適化を迅速に進めるのに都合がよい方法だからである。持ち株会社化を行う理由には大きくわけて以下2つがある。
(1)グループ内の事業再編を行う必要がある場合
グループ内で事業再編が求められる理由の一つに、経営資源の再分配があげられる。 企業が競争力を高めていく上で、経営資源の最適配分を行い、意思決定を機動的に行う事は不可欠だ。
そこで純粋持ち株会社をグループに設立することで戦略レベルの意思決定と経営管理の機能を持ち株会社に集中させる一方、別法人化した事業部門にオペレーションレベルの意思決定と採算責任を委譲することで、経営資源の再分配を効率的に行うことが可能となる。
例えば、X社がA事業、B事業を行っており、純粋持ち株会社を設立する場合は以下のようになる。
(例)<純粋持ち株会社化前>
X社(A事業とB事業を行っている)
↓
<純粋持ち株会社化後>
X社(純粋持ち株会社)
│ │
Y子会社(A事業) Z子会社(B事業)
(2)経営統合を行う必要がある場合
経営統合を行う際に、合併して一つの会社にすることで、統合のスピードを上げることは可能だ。
しかし、合併にはシステムの統合や企業文化の融合など課題や障害も多く容易ではない。また、合併では異議催告申し立て期間を1ヶ月置く必要があるが、株式移転による純粋持ち株会社化を行う事で同期間を短縮可能であり、許認可の継承に係る事務手続きも無くなることも純粋持ち株会社化が採用される要因と言えよう。この手法により共同の純粋持ち株会社を設立し、その持ち株会社に両企業を保有させた上で、段階的な統合を進めることで、合併による一時的な弊害を取り除くことが可能となる。
例えば、A事業を行っているX社が事業拡大を図る為に、同業のY社と経営統合を検討したというケースを想定すると、次のようになる。
当初X社は合併を想定していたが、Y社とは、給与体系などの企業文化や制度に違いも多く、短期的な統合には障害があることがわかった。
そこで、両社共同で純粋持ち株会社Z社を設立し、X社とY社をZ社の傘下にすることにした。
これによって、X社とY社は兄弟会社となり、段階的に制度・システム・リソースの統合を別法人のまま進めることが可能となる。
上記を図にすると以下のようになる。
(例)<純粋持ち株会社化前>
X社(A事業)、Y社(A事業)
↓
<純粋持ち株会社化後>
X社株主 Y社株主
│ │
Z社(純粋持ち株会社)
│ │
X社(A事業) Y社(A事業)
しかし、この形態が継続する場合、両子会社の間で管理や事業の重複、コストの無駄、戦略の矛盾が続く恐れもあり、企業文化や制度の統合が遅れることもある。その場合は何のための経営統合だったのか解らなくなってしまうことも有り得る。また、連結納税制度の利用など、税務面でも最適な統合スキームになり得るかどうかも検討する必要がある。一口に経営統合と言っても最適な形態は個別企業の戦略や業界構造、パートナー、課題の優先順位に応じてケースバイケースである。どのような統合形態を選択するか入念な検討・調査が求められる。
<篠崎 暁>