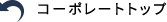自動車業界ライブラリ > コラム > 10 代目カローラの製品開発からのインプリケーション
10 代目カローラの製品開発からのインプリケーション
◆トヨタの渡辺社長「『大衆車』という概念でものづくりをすると間違う」
<2006年10月18日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10月 10日、10 代目カローラが発表された。今回はこの世界で最も売れている乗用車を題材に、トヨタ・日産・ホンダの 3 社の製品開発のプロセスと体制の違いを概観し、自動車メーカーにてベンチマーキングを担当されている人たちや、自動車産業への新規参入を検討中の異業種企業へのインプリケーションを提示してみたい。
【製品開発のファクター】
自動車の製品開発において、その総責任者(主査。トヨタでは CE)に指名された人間がまず行わなければならないことは、主査構想、つまり自分がどんなクルマをどのように作るのか、をまとめて機関(通常は役員会)承認を取ることである。主査構想に含まれるべき要素は、凡そ次の通りである。
・商品コンセプト(標的顧客層の設定、当該顧客層に感じてもらう製品のうれしさ・ありがたみの定義、うれしさ・ありがたみの実現方法の特定)
・パッケージング(内外の空間寸法)
・スタイリング(外観、内装、カラー)
・パフォーマンス(性能、品質、重量)
・ファンクション(装備、仕様)
・リソース(原価、工数、時間)
10 代目カローラを開発した藤田博也 CE の立場に立って、製品の 4 要素であるパッケージング、デザイン、パフォーマンス、ファンクションをどのように決めていったのかを追体験してみよう。
なお、今回のカローラから国内仕様(アクシオ、フィールダー)と海外仕様(おそらくオーリス・ベース)が分かれることになり、開発も多くの点で別々に行われている。ここで述べていくのは国内仕様についてであり、競合比較に用いているのは主に伝統的なセダン(アクシオ)の 1.5 リットル版(G グレード)である。
1.パッケージング
商品コンセプトを固めたら次に主査が取り組むべき課題はパッケージングである。想定した顧客層の属性や行動様式、生活環境からして自動車がどんなシーンで使用されるのかを想定し、そこから空間の形状や大きさを決め込んでいく。人間の居住スペースだけではなく、求められるパフォーマンスやファンクションを実現するためのデバイスがどんなものであるかを想定しながら、それを搭載するためのスペースやレイアウトを考えていかなければならない。
グローバル市場を対象にする製品であれば、世界各地での使われ方や製品の位置付けや性格、期待役割、制約条件等を考え合わせていかなければいけない。
作り手側の事情としても、リソース(原価、工数、時間)の制約やブランドとしての一貫性、他の製品とのカニバリゼーションなど頭の痛い問題もあるから、何でもかんでも新開発、専用設計というわけにも行かない。さらに海外でも生産されるようなら海外生産固有の課題も考慮する必要がある。
カローラの場合、日本では高齢者が主要顧客であり、市場も縮小していることから、今や必ずしも顧客のトヨタブランドとの出会いやトヨタのビジネスの中核を担う車ではなくなっている。だが、世界 147 ヶ国で売られるトヨタの主力車種であり、国によって法規制や自動車に求められる要件が様々である上に、カローラという製品の性格も若年層の人気車であったり、高級車であったり、トヨタという社名以上に車種ブランドが浸透していたりと多様である。
また、世界 16 ヶ国で生産される製品であるため、海外生産拠点の設備や組織、人員、サプライヤの能力も踏まえた製品開発が必要になる。特にトヨタは将来世界同時立ち上げを計画しており、10 代目では切り替え時期の内外格差を過去最小にすることが制約条件になっていたと思われる。
もう一つ考慮すべき点があるとしたら、カローラは 9 代目で「ニュー・センチュリー・バリュー」というテーマで、相当の投資もして一から設計を起し直しており、市場の評価も高いことであろう。
こうした前提条件を踏まえて、トヨタが出した結論は、海外向けはワイド・ボディ(オーリス・ベースだと思われる)で行くが、国内用に 1700mm 以下のナロー・ボディも用意するということであった。
その上で、藤田 CE が国内用に出した判断は、原則として先代のレイアウトを継承するというものである。パッケージングの変更は、ヒップポイントを下げてヘッドクリアランスを広げたり、フロアトンネルの段差を極小化して足元のスペースを広げたりすることに留めている。
この結果、パッケージング的には突出した点は少ないものになっている。
全長は日産ラティオより僅かに長いのに室内長では 8.5cm 短い。全高で劣るからやむをえないとはいえ室内高も 3.5cm 低い。フロアもホンダ・シビックほどにはフラットでない。
2.スタイリング
今回のデザインテーマは、外観では「アクティブ&プレミアム」、内装では「躍動感と質感」、カラーでは「和(繊細で上質)と洋(アクティブでスタイリッシュでモダン)」だという。
デザインの 3 大領域のテーマは統一されている。10 代目カローラの使命の一つが、国内で 60 代の固定客の取りこぼしをなくすとともにその下の 50 代の客層を新たに取り込むことであった。バブル崩壊後に開発された 8 代目を除けば「プレミアム」の追求が 40年間ほぼ一貫した方向性だったが、これに「アクティブ」の要素を加えたことはミッションとの整合性がある。
また、アクシオは国内専用だが、インテリアは海外も基本線は共通だと聞く。海外市場がカローラに求める価値も概ねアクティブかプレミアムのどちらかであるから、その点でも整合性が取れている。
スタイリングは他社との定量的な比較ができず、デザインテーマがミッションに忠実だったからと言ってその結果もミッションとマッチしているとは言い切れない(特にフィールダーの内装色)。だが、既成概念を取り払う取り組み(フィールダーから先にデザインする、居住性や剛性を犠牲にせずに視覚的に躍動感や伸びやかさを見せる手法を採用)などの野心的試みも多く、新しさ・美しさを感じるとするメディアが多いようだから、成功だと言えるだろう。
3.パフォーマンス
10 代目のカローラは 1.5 リットル、1.8 リットルの 2 つのエンジンを用意しているが、新開発は後者のみ。主力となる前者は先代の後期モデルの改良版で、出力・トルク・燃費性能(実用燃費との乖離は小さいらしいが)は日産ラティオと同等である。
トランスミッションにはエンジンとの統合制御を行い、動力・燃費性能を高めた新開発の CVT を採用している。日産ラティオのエクストロニック CVT も同様のコンセプトだが、カローラの場合、カーナビと連動した変速制御や、無断変速にも拘らず敢えて 7 速 AT 的な使い方ができるような仕掛けを用意している点がユニークである。
ステアリングは競合車と同じ EPS で、最小回転半径が競合車よりも若干短い。サスペンション・レイアウトは先代のものを踏襲している。
ブレーキには EBD を採用し、後輪の制動力を向上させているが、これはホンダ・シビックも採用しているものである。
日産ラティオとホンダ・シビックが装備しているリヤスタビライザは装着していない。
車重は 1.8 リットルエンジンのホンダ・シビックよりは 80 キロ軽いが、同じ 1.5 リットルの日産・ラティオよりは 30 キロ重い。
結論として、競合比較ではほぼ互角と言ってよいだろう。
4.ファンクション
藤田 CE は今回のカローラの最大の売りを「インテリジェント機能」に置いたと言い、リアビュー・モニターが標準設定、パーキング・アシストが 4 万円台のオプション設定、プリクラッシュ・セーフティはグレード設定となっている。
競合車は持ち合わせていない装備であり、今回のカローラの最大の差別化要因であるとともに、高齢化が進んだ国内の標的顧客に感じてもらうべきうれしさ・ありがたみを直接的に実現する手段となっている。
【製品開発のプライオリティ】
以上、パッケージング、スタイリング、パフォーマンス、ファンクションの4 つの商品要素をレビューしてきたわけだが、藤田 CE がどの分野にプライオリティを置いたか、つまりどの分野で顧客に対するうれしさ・ありがたみの提供や競合・先代に対する差別化を実現しようとしたか、どこに新開発・専用設計など開発リソースを重点配分しようとしたのか、を考えてみたい。すると、凡そ次の順番であったと言えるのではないだろうか。
<カローラ>
ファンクション→スタイリング→パフォーマンス→パッケージング
ファンクションには他の追随を許さない新技術を搭載し、スタイリングも商品コンセプトとの整合性の高いものであった。だが、パフォーマンス面では新開発・専用設計が少なく他社並みの性能に留まり、パッケージングはほぼ先代の踏襲で競合優位性は殆ど見られないからである。
同じように、日産ラティオやホンダ・シビックのプライオリティを考察してみる。
<ラティオ>
スタイリング→パッケージング→ファンクション→パフォーマンス
<シビック>
パッケージング→スタイリング→パフォーマンス→ファンクション
日産ラティオの場合は、自動車らしからぬインテリア・デザインのモダンさと、競合との比較で最短の全長(ルノー・クリオと共有の B プラットフォームを用いる関係と思われる)にも拘らずシーマ並み(もちろんクラス最長)の室内長を持つパッケージングを売りにしている。
その代わり装備(ファンクション)面で特筆すべきものは、木目調パネルであったり、リアシートのヘッドレストであったり、スタイリングに関わるもの以外には少ない。
パフォーマンスという意味では、新開発のエンジンと FR の高級車から移植したトランスミッションを持つものの、これは他の車種との共有を前提にしたもので専用設計ではなく、スペック的にも今や平凡である。
ブログやユーザーサイトを見る限り、顧客の評価も上記の順番のようだ。
ホンダ・シビックの場合は、国内仕様だけを見ていると寧ろ全くパッケージングを無視しているように見えるかもしれない。このクラスでは国内で嫌われる 3 ナンバーボディを持ちながら室内長や室内高ではカローラやラティオに明らかに劣る。
だが、グローバルに見ると話は異なる。北米にはセダンのみならず 2 ドアクーペも用意し、欧州には 3HB/5HB を投入している。市場の特性やそこでのシビックの位置付けや役割、使われ方に応じて市場別に最適なパッケージングを開発しているのである。(日本仕様のシビックが必ずしも国内最適解になっていないのは、おそらく日本では海外でシビックが果たしている役割をストリームなど別の車種に担わせているためだろうと思われる。)
10 代目カローラも国内と海外を分けているが、意味合いはやや異なるだろう。もし、それがカローラでなかったなら、カローラに対する思い入れがなかったとしたら、オーリスがカローラになっていた可能性が高いのではないだろうか。
ホンダ・シビックのようにパッケージングの市場最適解を求めてアクシオが誕生したわけではないと思われる。
市場別にボディまで変えてしまう(つまり市場別に別々の開発と設備の投資が必要となる)パッケージングであるから、当然スタイリングにプライオリティを置いていると言えるし、そうせざるを得ない。欧州用の HB のバックドアは特別な樹脂で構成される。競合車に対しても前後とも 1 インチ大きく扁平率の高いタイヤを履いている。
これに対して、パフォーマンスは水準自体を競合他社よりも高いところに設定しているものの、市場ごとに新開発・専用設計するではなく、ほぼ世界共通のスペックを持っている。
エンジン・ラインナップは競合より一回り大きい 1.8 リットルと 2.0 リットルの組み合わせで、リッターあたりの出力・トルクも大きいが、これは世界共通である。シャシーにはダブルウィッシュボーン式のサスペンションやトラクション・コントロールが付き、ブレーキは後輪もディスクであるが、ほぼ世界共通である。視認性というパフォーマンスを重視したものと思われる上下二段式のコンビネーションメータも他社にはない特徴だが、世界共通である。
ファンクションと言う面では競合他社に比べて貧弱で、市場別に固有の設定も少ない。オーディオはラジオすら付いていないし、競合車にはない前横プロテクタの装着も機能性ではなく、デザイン性を狙ったものと考えられる。
あらためて 3 モデルの製品開発のプライオリティを並べてみる。
<カローラ>
ファンクション→スタイリング→パフォーマンス→パッケージング
<ラティオ>
スタイリング→パッケージング→ファンクション→パフォーマンス
<シビック>
パッケージング→スタイリング→パフォーマンス→ファンクション
・スタイリングは、各社とも高い優先度を置くファクターだが、中でも日産が最も高い
・逆にパフォーマンスは、各社とも(このクラスでは)あまり重視していないが、ホンダは比較的力を入れている
・パッケージングは、ホンダと日産にとっては優先度の高いファクターだが、トヨタではあまり高くない
・逆にファンクションは、トヨタにとっては優先度の高いファクターだが、日産、ホンダではあまり高くない
【製品開発の体制】
同じセグメントに属する 3 モデルの製品開発のプライオリティに差が生まれる背景には、もちろん各モデルの標的顧客層や競争ポジショニング、自社内での位置付けの違いがあるだろう。だが、原因はそれだけではなく、各社の組織体制の違いによる構造的な原因もあるのではないかと思われる。同じようなことが他の車種でも起きているからである。
<トヨタ>
トヨタは、1992年に主査(CE)制を維持しながらセンター制に移行している。
デザイン(2003年にセンターから独立)・設計・実験などの技術部門を製品群別に 4 つ(その後 5 つ。2003年に要素技術開発、先端技術開発が本部に改組され、現在は 3 つ)の開発センターに分解して、技術部門全体に対して主査の目が届きやすいようにして相対的な発言権も再強化したものである。
同社は主査制の草分け(1953年)であり、製品開発の全ての権限と責任を主査に集中させることで意思決定を早め、製品としての一貫性や品質を高めることに世界で最も成功してきた会社である。
しかしながら、同社の車種が増え、技術が高度化し、社内の組織も専門化すると、一人の主査が全社を見渡して有効活用できそうな製品・技術ストックを見つけ出すことが困難になり、工数や原価の無駄が増え、社内調整に時間を要するようになってきた。
しかも、その頃同社は大型の設備投資時代に入っており、90年代だけで海外を含む 9 工場・事業所の操業開始が予定されていたのに、80年代後半には急激な円高が進み、90年にはバブル崩壊で最大 250 万台に達した国内販売台数が現在の 170 万台レベルまで急減する節目にあった。そこで全社を横断的に見られる立場の技術部門が効率追求のために力を付け始めたのである。
しかし、その結果、作り手の論理が蔓延し、意思決定も遅くなっていった。80年代の GM との米国合弁事業を通して GM の意思決定の早さに接して、そのことに気付いたトヨタでは 1989年頃から上述の組織変更に着手し、1992年に実行に移したのである。
センター制が効果を発揮したことは明らかである。60年代~ 80年代までの 30年間に同社が発表した新型車は全部で 31 車種だったが、90年代の 10年間だけで 29 車種を発表しており、開発のスピードが速まった。
主査制・センター制の長所としては、意思疎通や情報共有が進み、組織内に歴史的に蓄積・面的に分散したリソースやアセットを効率的に活用できることで、世界全体最適性を維持しながら Product (製品)としての継続性、統合性や機能性を高めることが可能になる。
反面、過度にそうした長所を強調しすぎると、イノベーションが生まれにくくなる。ニュー・センチュリー・バリューの開発を目指した 9 代目カローラの初期デザインが否定された理由もそこにあると思われる。カローラには「80 点+α主義」という伝統があり、「+α」のエッジが求められているのに「80 点」の方ばかりが前に出てしまう恐れがあるのである。
10 代目カローラでは、パッケージングやパフォーマンス面では大きな冒険はせず、世界全体最適と Product としての完成度で標準化の方向性を目指した。
逆に、ファンクション面とスタイリング面で顧客価値の創造や、先代・競合との差別化を図ることで個性化を図り、バランスを取っている。
トヨタの組織構造から生まれる必然的なアウトプットであると考えられる。
<日産>
日産の製品開発組織は、4 チーフ合議制とコミットメント制に特色がある。
同社は、カルロス・ゴーン氏の COO 着任直後の 2000年に主査(同社では商品主管)制を解体して、商品・デザイン・開発・マーケティングの 4 チーフ合議制に移行している。また、同時に開発本部内にあった商品企画とデザインの部署を開発本部から切り出して本部に昇格させて開発と同格とした。
その背景にはルノーの資本参加の要因となった日産の販売不振、業績悪化がある。同社ではその原因が製品ごとの市場評価にバラつきがあり、それが他社に比べて大きいことにあると分析した。さらに商品主管が原価・工数管理や計画の進捗管理、市場導入まで全部を預かるために商品企画に集中できないことと、商品主管ごとに力量の差があることがその原因だとの判断から、そうした構造を生んでいる主査制度を解体して、個人の守備範囲を限定するとともに、全社的な能力・スキルを活用して個人的力量の限界とバラつきをなくそうとしたものである。
4 人のチーフは、各々年俸の掛かった定量的なコミットメントの達成責任を持っているから、合議制と言っても安易に譲ることはできない。商品を預かるCPS (チーフ・プロダクト・スペシャリスト)や市場導入を預かる CMM (チーフ・マーケティング・マネージャ)としては、パッケージング、パフォーマンス、ファンクションを専用設計・新開発したいはずである。だが、原価と工数を預かる CVE (チーフ・ビークル・エンジニア)としては安易に妥協するわけにはいかない。
4 チーフ合議制とコミットメント制の長所は、ブランドとしての一貫性が担保されるとともに、Merchandise (商品)としてのバランスが取れることである。
製品単位で総責任者を決めていくと個々の製品としては完成度が高く、全体最適が取れていたとしても、ブランド全体を通して、もしくは商品体系全体を見ると整合性のない製品が生まれかねない。その弊害を排除しやすくなる。
また、主査個人の主観の偏りや誤りを専門分野ごとにコミットメントを持つ複数の人間同志で相互牽制できるから、Merchandise としてのバランスが取れるようになる。
日産ラティオのケースでは、対立する価値観・意見を調整・集約した結果、比較的原価・工数負担の少ないスタイリング(特にプレス金型や溶接設備への投資や衝突安全性の解析工数などが少ないインテリアとカラー)による個性化を最優先し、パッケージングでは汎用プラットフォームをレイアウトで工夫して使うことで個性化と標準化のバランスを取り、パフォーマンスとファンクションの面では標準化方向に振るという結論に落ち着いたものと思われる。
日産の組織構造を考えると、理解し易い結果である。
<ホンダ>
ホンダの製品開発組織の特徴は、タスクフォース制とマトリクス制である。
同社ではある製品の開発指示が出ると、都度、S (営業)・ E (技術開発・生産)・ D (製品開発)の 3 部門を中心にタスクフォース型の開発チームを組成し、開発が完了すると解散する。開発の初期段階から非技術部門が加わることも他社にはあまり見られないことだし、他社では製品開発完了後も開発した車種の販売が続く限りは開発チームが継続して責任を持つのに比べると異例である。
また、同社の組織は市場軸の地域本部と製品・機能軸の事業本部のマトリクス組織となっている。どちらがより強いかと言えば、市場軸の地域本部が主導権を握っており、製品・機能軸はその支援と調整の役割である。
ホンダの製品開発は元々本田技術研究所にかなりの部分が任されていた。本田技研の役割は開発指示までと生産・販売で製品開発工程は別会社の仕事になっていたのである。その背景には、四輪では後発ゆえに製品・技術による差別化が必須だと考えられていたことが挙げられる。ところが、1990年代に入って販売不振と業績悪化が続き、その原因がプロダクトアウト的なものづくりの行き過ぎによって顧客ニーズとのずれや開発コストの高騰を招いたことにあったのではないかとの反省が生まれた。
1994年 3月期に業績が過去最悪となった後、同社はそれまで徐々に進めてきた組織改革を集大成して実行した。地域本部に四輪・二輪・汎用機の S ・ E ・D 全ての責任と権限を委譲するとともに、本田技研本社に四輪事業本部を設置(1986年の推進チームから発展)して同事業本部に地域本部の支援と世界全体最適・長期最適の調整の役割を与えたのである。これにより、製品開発は地域本部の計画をもとに四輪事業本部が調整を行って本田技術研究所をコントロールしながら進めていく顧客志向と管理体制が強化された。
ホンダの体制のメリットは、市場別に商品の最適化・ラインナップの一貫性が取れるようになり、Goods (身近な品物)としてのタイムリネス(適時性)が保証されることであろう。
この体制の下で開発された代表的なモデルが 1997年のアコードである。日・米・欧・アジア大洋州の世界四局で別々に開発・生産されたパッケージングとスタイリングをまといながら、パフォーマンスとファンクションの多くは世界共通となっている。
8 代目シビックでも同様で、パッケージングとスタイリングで市場と時代への適合性という形で個性化を実現するとともに、パフォーマンス面では汎用化のレベルを高めることで個性化と標準化のバランスを取り、ファンクション面での標準化を目指している。これもホンダの組織構造から見ると自然な落ち着きどころだと考えられる。
【まとめとインプリケーション】
以上見てきたとおり、個性化と標準化のバランスは自動車メーカー共通の課題である。違いは、企業として何を重要視しているのか(企業戦略)、そのために製品としての均衡点をどこに置くのか(製品戦略)、均衡点に達するためにどんな仕組みを用意するのか(組織戦略)の差であろうと思う。
3 社の違いは、次のように整理できるのではないかと考える。
<トヨタ>
・企業戦略: 世界全体最適と Product としての完成度
・組織戦略: CE 制とセンター制
・製品戦略
標準化: パッケージング
両立化: パフォーマンス
個性化: ファンクションとスタイリング
<日産>
・企業戦略: ブランド最適と Merchandise としてのバランス
・組織戦略: 合議制とコミットメント制
・製品戦略
標準化: ファンクションとパフォーマンス
両立化: パッケージング
個性化: スタイリング
<ホンダ>
・企業戦略: 市場最適と Goods としてのタイムリネス
・組織戦略: タスクフォース制とマトリクス制
・製品戦略
標準化: ファンクション
両立化: パフォーマンス
個性化: パッケージングとスタイリング
このような違いが生まれた背景には、既に見てきたように各社が置かれてきた歴史的な経営環境や競争ポジションの違いがある。同じ自動車メーカーだからと言って、また課題が共通だからと言ってひと括りで論じることはできない。
ということは、次の二つのことがインプリケーションとして言えると思われる。
1.ベンチマーキングの視点
自動車メーカー各社が自社の製品開発戦略の妥当性を検証しようとする場合、競合他社をベンチマーキングすることが適切とは限らない。寧ろ、自社と同じような歴史的環境や競争ポジションにある自動車業界以外の事例に目を向けた方が効果的な場合もある。
2.新規参入の視点
新たな技術・製品提案により自動車産業に新規参入を検討している企業は、どの自動車メーカーに提案を持ち込むのが効果的かを事前に検討しておく価値がある。自動車メーカーの年表と組織図と製品カタログがその材料になる。
<加藤 真一>