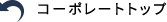自動車業界ライブラリ > コラム > 垂直統合戦略展開時のコンフリクトをどう解消するか
垂直統合戦略展開時のコンフリクトをどう解消するか
◆部品商を整備アドバイザーに ボッシュ教育に着手
<2006年06月29日付日刊自動車新聞掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ボッシュの試み】
米デルファイを抜いて OEM サプライヤとして世界最大となった独ボッシュは、同時に点検・整備用の設備・機器と市販用の部品・用品のメーカーとしても大手である。同社は、数年前から日本国内で街の(つまりディーラー以外の)整備工場にボッシュ・カー・サービス(BCS)なるブランドを与えて独自の整備工場の組織化に乗り出している。国内で特定の機材・部品メーカーのブランドを冠した整備工場チェーンは他に例がない。
BCS は 1997年に本国ドイツで始まり、いまや世界中で 1 万店を数える巨大ネットワークに成長している。だが、国産車が市場を独占する日本においては、輸入車に強い(逆に言えば国産車に弱い)と評価されがちなボッシュ製品はディーラーでの採用拡大が期待しにくい。
従って、街の整備工場はボッシュにとって国内で最重要顧客である。その最重要顧客を他社製品に浮気させないために、この仕組みは国内において戦略的に特に重要な意味を持つと考えられる。
現在、国内には 100 店の BCS 工場が存在するが、日刊自動車新聞の報道によれば、ボッシュは 2008年までにこれを倍の 200 店に増強させる計画である。
街の整備工場は全国に約 8 万社もあることを考えると、それでもまだ小さな数字ではあるが、街の整備工場の側でも近年整備単価の低下やディーラー工場への顧客流出が顕著で、差別化が課題になっていることから、注目すべき動きの一つだといえよう。
そのボッシュが、BCS 拡大のため新たな試みを発表したと日刊自動車新聞は報じている。市販用部品流通のバリュー・チェーンにおいて二次または三次卸の機能を持つ地域部品商向けの教育・研修活動に着手したという。
研修の内容は、最新の自動車に搭載されている技術知識、最新の点検・整備用設備・機器に関する商品知識、その両方を組み合わせた最新の点検・整備技術知識のようである。
部品流通を通じて街の整備工場との間に太いパイプを持つ地域部品商に教育を施して、整備工場のコンサルタント的な存在に育成して、BCS の裾野拡大や地盤強化に繋げようという狙いと考えられる。
最新の自動車にはコンピュータとエレクトロニクスが多用されており、機械的には故障診断が困難になる一方、電子的診断は容易になってきている。うまく最新の知識・技術・装置を使えば整備工場の生産性や収益性の向上に繋がる可能性がある一方で、そうでなければ点検にも整備にも着手すらできないという悲惨な状況が生まれかねない。
従って、電子的な故障診断システムなどエレクトロニクスに強い製品を主力とするボッシュにとっては大きなチャンスが生まれている。整備工場の関心や知識・技術が高まれば高まるほど、自社製品のシェア(BCS 工場の数と各工場の投資余力増大)とロイヤリティ(各工場の自社製品への依存度)が高まり、事業の成長性と安定性が同時に高まることになるからである。
そうした中、自社が直接街の整備工場に対する教育・研修活動に乗り出すのではなく、地域部品商を通じて間接的な方法で整備工場の関心・知識・技術強化に繋げていこうとする意味はどこにあるのだろうか。
教育・研修の綿密さと範囲の条件を同一とした場合、自社リソースを使うよりも彼らに外注した方が遥かに安上がりだという判断があるだろう。というのも、地域部品商という外部リソースには固定費がかからず、日常的に BCS 工場と幅広く接しているから、指導のための変動費も最小化できるからである。
だが、本当にコストだけがドライバーなのだろうか。実際、アウトソーシングにはマイナス面もある。外部リソースである以上、必ずしもボッシュの思惑通りに動いてくれると期待できるわけではない。全国に 1 万社ある地域部品商の多くは、特定のブランドや系列からのみ商品を仕入れるのではなく、顧客である街の整備工場の求めや自社の利益(売りやすさ、儲け)に応じて、メーカー系の部販・共販からは純正品を、全国卸からは優良品を、場合によっては中古品や輸入品をかき集めてくる存在である。
ボッシュの教育を通じて、技術コンサルティング能力を高めて街の整備工場の信頼を獲得して絆を強めた地域部品商が、自らに都合のいい他社製品を持ってくる可能性は排除できない。コストが安い分だけそのようなリスクもある。
それでも敢えて地域部品商という既存の流通事業者をパートナーとして自社の
戦略に組み入れた背景に注目したい。
【アスクルのビジネスモデル】
今回のボッシュの試みから連想されるのは、オフィス向け文房具・事務用品のカタログ通販・ e コマース会社のアスクルである。
同社は、中堅文房具メーカーのプラス株式会社の一事業部門としてスタートしたのが 1993年、独立会社化したのは 1997年と新しい会社だが、2000年には東証一部に上場し、現在は年商約 1500 億円と親会社の 3 倍、トップ文房具メーカーのコクヨに対しても半分の規模にまで急成長した。
つい 10年前まで文房具業界の売上は、文房具店の店頭での棚割り面積によって決まっており、どこの文房具店でも最も広く見やすいスペースは最も売れ筋のコクヨ製品に割いてしまうから、中下位メーカーが売上を伸ばすことは容易ではなく、業界の序列は永遠に変わりようがないと見られていた。
中堅メーカーのプラスから生まれたアスクルは、革新的なビジネスモデルによって業界の常識を覆したカテゴリー・キラーである。そのビジネスモデルの革新性は経営学者やコンサルティング・ファームの注目の的であり、ビジネススクールでもケーススタディの題材として取り上げられることが多い。
よく指摘されるのはアスクルの次のような独自性である。
それまで業界が無視していた巨大需要を掘り起こそうとした着眼点(日本の文房具需要の 75 % は法人需要であり、全法人の 95 % は従業員 30 人以下の零細事業所なのだが、殆どの文房具店は個人と大手企業ばかりを顧客ターゲットと想定していた)、IT (SCM)を活用した即納体制(明日来る)の確立、敢えて自社(親会社)の競合製品をも取り扱うという顧客志向のマーチャンダイジング、流通簡素化(カタログ販売、直接納入)による低コスト化の実現と、その結果としての低価格化の成功、等々である。
だが、筆者が最も関心を持つのは、アスクルが街の文房具店をビジネス・パートナー(同社ではエージェントと呼ぶ)として、自社のバリュー・チェーン、ビジネスモデルの枠組みの中に取り込んだ点にある。
今更ながらではあるが、少しおさらいをしておくと、アスクルのバリュー・チェーン、ビジネスモデルは次の流れ・構造になっている。
まず、アスクル自身がマーチャンダイジング(品揃え、値付け)、商品カタログ製作、物流システム(仕入れから納品まで)の構築を行う。
次に、エージェントである街の文房具店が、地域の中小企業に出向いて、アスクルのシステムを説明し、商品カタログを置いてくる。
商品カタログを見た中小企業からのオーダーはアスクル自身が受け付けて、受注後直ちに直納するとともに、エージェントに対して受注・納品情報を連絡する。
最後に、エージェントが中小企業に出向いて代金を回収してくる。
つまり、規模の経済が求められる部分(集中購買、カタログ製作、システム構築)と、サービスの均質性や効率性が求められる部分(品揃え、値付け、コールセンター、ロジスティクス)はアスクル自身が一元的に請け負う。一方、顧客インターフェースの多様性や柔軟性が求められる部分(顧客開拓と代金回収の業務とリスクの負担)は街の文房具店の機能に一任する、という分業が成立している。
単純なカタログ販売や e コマースとはこの点で大きく異なるのである。一般にカタログ通販や e コマースの流通は既存業者の関与がなくても成立可能であるし、寧ろ既存事業者の存在はコストとリードタイムの無駄として排除されることの方が多い。
また、アスクルには既存事業者を排除しにくいというイノベーションのジレンマも相対的に少なかった。麒麟麦酒が既存の酒屋ルートのしがらみを断ち切れずにいる中で、酒屋ルートに弱かったアサヒビールが飲食店への直販ルートや消費者向けの量販店ルートを次々に開拓して行ったのと同じ戦略を取ることが可能なポジションに中堅メーカープラスはいたはずである。
にも拘らず、敢えて既存の流通事業者とのパートナーシップを取ったところにアスクルの独自性があり、それがアスクルの強みや急成長の原動力になったと筆者は考えている。その結果として、業態認知や顧客基盤の獲得の時間とコストを大幅に節約でき、顧客満足強化のための投資やオペレーションに集中することが可能になり、気が付けば大手企業が後発で参入してきても負けることのないビジネス・システムが確立されていたからである。
【アスクルのパートナー戦略】
アスクルがこのようなパートナー戦略を取った背景には 3 つの内部事情があったと思われる。
第一に、当時のアスクルには出来るだけ早く、多くの顧客と直接対峙する土俵を作らなければいけないという内部的な必要性があった。
潜在的な巨大市場を相手にしたシステム的なアプローチであるから、大規模展開でなければペイしないが、インターネット時代到来という時代背景の中で市場の創出・浸透に時間を掛けていれば投資力に勝る大手にしてやられかねないという危機感があったはずである。
第二に、当時のアスクルは早く、多くの顧客と直接対峙するために必要な知識・経験やリソースを内部的に欠いていた。
直販経験を持たないメーカーから出発しているのだから当然のことで、せっかくカタログを製作しても、全国 600 万箇所の事業所のどこにそれを持っていけばいいのか知らないし、知っていてもそれをデリバリーする要員も持っていなかった。また、せっかく注文が入っても、個々の事業所の信用を審査する術も工数もないから代金確保前に商品を発送できない(明日来るにならない)、
発送したとしても代金回収ができない。
第三に、アスクルが早く、多くの顧客と直接対峙する上で、自らが本当にやりたいこと、やるべきことは全体の中でどこの部分なのかを認識したことである。
メーカーから出発したアスクルが自らやりたかったこと・やるべきだと考えたこととは、顧客が欲する商品を用意すること、それを顧客の望む価格、スピード、頻度、方法で提供することであったはずである。
これに対して、全国 600 万事業所をくまなく訪問して有望な客先を探し出すこと、カタログを配ったり、代金回収をして回ることは、自社の知識・経験・リソースを冷静に評価すれば、決してやりたいことでも、やるべきことでもないという判断に至ったものと思われる。
この 3 つの要素を考え合わせると、分業パートナーが必要となり、パートナー候補として街の文房具店の活用という構想が生まれてきたことは必然的とも考えられる。だが、だからといって単純にすぐこのパートナー戦略が是認されたわけではないだろう。次のような反対意見が出てくると予想されるし、その意見には一理あると言わざるを得ないからである。
「リアルの世界で生きる街の文房具店にとって通販・ e コマース市場が隆盛することは死活問題であり、通販・ e コマースは仮想敵のはずである。また、もともと他社の商品も平気で扱う非独占的事業者であり、ロイヤリティも低い。従って、有望な客先を見付けてきたら、それをアスクルに繋ぐことなく自分自身のビジネスに取り込んだり、アスクルの競合企業に持ち込んだりする行動を取らないとは限らない。」
個々にそのようなトラブルが実際に発生したかどうかは知る由もないが、その後アスクルが他社製品も扱う決断をした背景には、このような懸念が現実のものとなりつつあったのではないかと想像される。つまり、顧客や街の文房具店からは、「アスクルのモデルはすばらしいが、プラスの商品ばかりでは魅力が小さい。アスクルで他社製品も扱えないか。」という声が出てきていたのである。結果として、アスクルは他社製品も商品ラインに加える決断をしたのだが、もしそうした声に応えていなければ、せっかくアスクルが創出した市場、ネットワークを大手文房具店や他の文房具メーカーに根こそぎ渡さざるを得ない危機が発生していたものと思われるのである。
【自動車業界課題への置き換え・アナロジー】
ボッシュの今回の試みや、アスクルのモデルを長々と説明してきたのは、それらが自動車業界が今後直面するシステム化・モジュール化の進展や、それに伴う素材メーカーの加工メーカー化、下位ティアメーカーの上位ティア進出といった垂直統合的な戦略遂行に際して、何らかの示唆や教訓を含んでいると考えるからである。
筆者は過去 2 回にわたって本誌で、今後自動車の設計思想、開発手法、部品や機能の括り方、自動車メーカー内部の組織やサプライヤとの関係性が、「道州制」的な大きな括り直しのもとでの分業体制に移行していくであろうことを述べてきた。
その主なきっかけは、マクロで見ると、自動車業界内部の課題の拡散により、自動車メーカーの内部リソースの分散希薄化が避けられない見通しであることだとしたが、ミクロな視点で見た場合も軽量化とコスト削減の要件が限界に達していることも大きい。
環境に対する社会的要件にミートするために自動車には一層の軽量化が求められる(そうでなければ内燃機関を本気で他の動力に置換していかなければならない)が、もはや素材の見直しなくして求められるレベルの軽量化は達成不可能な段階にきている。だが、軽量素材は一般にもともとの材料費が高価な上に、自動車に対するもう一つの社会的要件である安全性への対応で特に剛性面での課題が残り、その克服のためのコストは一層割高になる。素材の高騰分を補って更なるコスト削減を進めようとしたら、重複投資、重複工程を極力減らしてバリュー・チェーン全体でコストを下げる以外ない。
自動車は必然的に軽量素材を使いながら、部品や工程の統廃合の方向に向かわざるを得ない、ということになる。
そうした中で軽金属や樹脂などの素材メーカーにはビッグチャンスが生まれるが、単に素材だけ提供するというのではこの大きな流れを引き寄せることは出来ない。
素材そのものはコスト削減の要件に矛盾しているし、異種素材間での競争もあるからで、バリュー・チェーン全体でコスト上昇圧力を軽減するためのものの作り方、機能のまとめ方を同時に提案していかなければ、他の新素材や工法を変えた既存素材に打ち勝てるとは限らない。私どもでも素材メーカーの仕事をお手伝いしているが、多くの場合、課題はそこにある。
その他の加工品サプライヤにとっては部品・工程の統廃合はピンチでもあり、チャンスでもある。
小物部品を作っているサプライヤや、製造工程に強みを持つサプライヤにとって、部品・工程が統廃合され、部品の数・形や括り方・作り方が抜本的に変わると、多くは淘汰される側に回ることになる。
だが、逆にシステム化・モジュール化のチャンピオンの側に回れば、従来他のサプライヤが得ていた付加価値分の仕事、自動車メーカーの業務範囲だった部分までの裁量権を得ることの出来る千載一遇の機会でもある。
先週、金属をスタンピングしてアウターパネルを作っているサプライヤ、樹脂の射出成型品を主体に内装品を作っているサプライヤの双方の話を伺う機会があった。前者は外側から進めるドアモジュール、後者は内側から進めるドアモジュールの開発を進めており、主導権(ティア 1)をどちらが取るかで、水面下で熱い戦いが繰り広げられている様子がひしひしと伝わってきた。
これら素材メーカーや加工品サプライヤの動きは、いずれも部品・工程の統廃合という必然的な業界の流れを踏まえて、事業領域を垂直方向に広げることで脅威を克服し、機会を捉えようとするものである。
だが、領域を広げた先には必ず既存のプレイヤーが存在する。そして、そのプレイヤーとは、従来のバリュー・チェーンにおいては自社の顧客であるという場合も多く、既存顧客との間でコンフリクトが生じかねない。
そこにボッシュやアスクルのケースから学ぶ部分があると思う。
【垂直統合戦略へのインプリケーション】
もし、自社が事業領域を垂直拡張していけば、既存顧客が仮想敵国に転じる可能性がある。そこで生じるコンフリクトをどのように調整・克服していくかが今後大きな課題になってくるだろう。大まかに分けると 3 つの方法があろうと思う。
第一に、競争で敵を打ち負かすという方法である。
第二に、M & A により敵を内部化するという方法である。
第三に、パートナーシップにより敵を味方に付けるという方法である。
どの方法にも一長一短あり、またケース・バイ・ケースで物理的に選択可能な方法、選択不可能な方法もあるから、一概にどの方法が最適かを論じることはできない。
だが、アスクルの項で、同社が考察したであろう 3 つの内部事情に触れたが、このような事情は多くの企業に共通するのではないかと思われる。少なくとも、同社やボッシュが取った第三の選択肢をそのような視点から整理して、自社の事情に適しているのかどうかを検討してみる価値だけは普遍性があるはずである。
<加藤 真一>