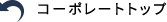自動車業界ライブラリ > コラム > 事業の「柔軟性」を高める
事業の「柔軟性」を高める
◆コマツ、自動車工場で稼働停止中のプレス機を買い取り、新興国に輸出へ
国内メーカーの余剰設備の整理を支援し早期の新規投資を促すとともに、拡大する中国やインド市場に中古ビジネスを強化し、足場を築く方針。
このほど新設した約 10 人の専属チームがトヨタグループなど顧客企業の計 100 工場に買い取りを打診する。
<2009年 07月 03日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【中古事業という新たな事業機会】
自動車を生産する上で多数の機械設備が必要になるが、その中でも大きな投資を求められるものの一つが、大型プレス機であろう。特にボディパネルやドア等の大型の外板を成形するプレス機は、かなり大きな投資を要する。金型のように、車種毎に用意する必要がある専用設備ではなく、数十年単位での稼動を前提に導入する汎用設備である。導入時にはある程度の稼働率で数十年間稼動させることを想定して数十億円単位の資金を投入することになる。
昨年来の経済不況の中、国内外の自動車メーカーは過大な製品在庫を調整するために減産を進めると同時に、設備投資も極力抑える傾向にある。当然、自動車メーカーに生産設備を納めてきた機械設備メーカーは、新規受注を期待しにくい環境に陥っている。
こうした中、今回のコマツが発表した戦略は、国内自動車メーカーが抱える余剰設備となっているプレス機を買い取り、生産能力が拡大傾向にある中国やインドなどの新興国市場に中古プレス機として輸出する、というものである。大型プレス機は耐用年数が長いので、国産の高品質のものが中古であっても安く手に入るということであれば、既に生産規模が回復している新興国市場での需要は少なくないであろう。近い将来、国内自動車メーカーが再び生産拡大する際にも、需要を喚起しやすいはずである。こうした中古事業に注力する機械設備メーカーは、今後増えそうな気配である。
【事業の「柔軟性」を高める】
近年の自動車業界の発展の歴史の中で、自動車の生産設備に対して、これまでテーマの一つとして掲げられてきていたのが、「柔軟性」である。市場の多様化に伴い、多品種少量生産を実現する混流生産の導入が進められるようになり、生産性を維持させながらも、金型や治具などの車種毎の専用設備を入れ替えられる「柔軟性」が追求されてきた。同時に、グローバル展開も進み、市場環境、労働力、生産規模など、生産ライン自体の多様化も進み、それぞれの生産拠点に最適なレベルでの自動化設計という「柔軟性」も求められてきた。
ただ、これまで追求されてきた「柔軟性」は、世界各地の生産拠点での生産能力拡大が前提となったものであり、継続する設備投資の中での「柔軟性」ともいえる。
昨今の経済局面において、大幅な減産を伴う生産調整が進められ、稼働率が低下する生産拠点も少なくない環境の中では、これまでの「柔軟性」で吸収できるものでもなく、人員、設備とも生産能力が余剰している状況にある。
これに対し、今回の余剰設備を買い取り、中古機械として新たな市場に再販していくというビジネスモデルは、生産拠点間、国境を越えたメーカー間での生産能力調整に寄与するものであり、これまでにない「柔軟性」を実現するものではないだろうか。
余剰設備を抱えるメーカーにとっては、資産の圧縮につながり、これから増産したい新興国メーカーにとっては、低価格で高品質な設備を調達することができるという両者にメリットをもたらす形となっている。
何より、機械設備メーカーにとってみれば、顧客である自動車メーカーの新規設備投入が低迷し、苦しい状況の中、低価格の中古機械設備を扱うことで、これまで価格競争が厳しくて参入できなかったような新興国メーカー向けにも供給できる可能性が高まるはずである。売上自体は新品の設備よりも少なくなるかもしれないが、機械設備自体が稼動すれば、中長期的な補修部品需要も期待できるはずである。
事業モデルとしても、自動車メーカー各社が設備投資を抑制する一方で、資本関係を超えた相互車種供給等の事業提携を進めつつある中、これから機械設備メーカーにとっては、定期的な新規機械受注を見越した事業よりも、中古機械の販売やメンテナンスでの継続的な売上にシフトする事業が有効なのではなかろうか。新車販売に苦戦する自動車ディーラーが中古車販売やメンテナンスにシフトするのと相似することを考えると、自動車生産設備の業界も成熟期に来ているのかもしれない。
【最後に】
経済環境が厳しい昨今、単に現状に甘んじるだけでなく、それぞれの市場環境に即した事業機会を探す余地はたくさんあるはずである。そういう意味では、自社の事業の「柔軟性」を高めることが重要であり、こうした事業を模索していくことが、再び景気が回復したときに大きく事業拡大することにつながるのではなかろうか。
<本條 聡>