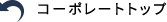自動車業界ライブラリ > コラム > 大企業の新規事業開発のススメ
大企業の新規事業開発のススメ
◆トヨタ、2020年代にはロボットを中核事業に
<2007年11月4日号掲載記事>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【新規事業開発の方向性】
トヨタが家事や介護を支援する「パートナー・ロボット」を実用化し、ロボット部門を中核事業の一つに育てる方針を「グローバルビジョン 2020」に明記したという。
日刊自動車新聞の月刊誌「Mobi21」にて同誌の編集人である佃義夫氏から「領域の拡大で、いずれはトヨタからモーター(自動車)という言葉が必要なくなるのでは」と問われて、トヨタの渡辺捷昭社長は「クルマが進化していけば、モーターではないのかもしれない。だから、モビリティという表現がいいのではないか」と答えている。
トヨタが Mobility メーカーだとすれば、その正常進化の先にロボット事業が浮上してくるのは当然である。
自動車はその価値を Liberty (社会的制約からの自由)→ Capacity (生産の制約からの自由)→ Property (表現の制約からの自由)→ Mobility (行動の制約からの自由)と変えてきた。Mobility の先には Ability (意思の制約からの自由)があり、それらは Quality (生き方の制約からの自由)という軸上での進化の過程を表していると思う。
パートナー・ロボットが提供する価値は Ability だと考えるから、Qualityの進化の過程で Mobility (自動車)の次に Ability (ロボット)が来ることは自然な流れだと思えるからである。
18 世紀後半にフランスで発明された世界最初の自動車(蒸気機関)は、その後蒸気船や蒸気機関車に発展し、市民革命という制度改革では支配からの完全な自由を手に出来なかった欧州市民に居住地や職業等の選択の自由を保証する移動手段を提供したという意味で Liberty (社会的制約からの自由)という価値を持った。
蒸気自動車は手作りで高コストだったため、実際に Liberty の価値を享受できたのは一部の市民だけだったが、19 世紀後半にドイツで内燃機関自動車が生まれ、1907年にフォードが T 型を開発し、その後 GM が商品ラインナップを多様化すると、安価で魅力的な自動車の大量生産が可能になり、一般大衆が自動車の価値を享受できるようになった。また、生産力が企業の競争力の源泉であり、企業の生産力によって国民経済の規模と成長が決まったという意味で自動車の価値は Capacity (生産の制約からの自由)にあったといえる(産業インフラ整備のために大量のバス・トラック・重機・建機が集中的に生産された少し前までの中国でも自動車の価値はそこにあった)。
国民経済が発達して、人口動態が活性化し、社会に正規分布的な所得・資産格差が存在するようになると、自動車の価値は所有を通じた成功や個性・属性の表現手段としての Property (表現の制約からの自由)に変わる。多様な乗用車が普及し、そのセグメント化と階層化が進む(少子高齢化前の多くの先進国・中進国や現在の中国)。
所得再分配を通して社会民主主義的な平等が達成され、人口動態の変化が停滞すると、差別化のための Property の価値は低下し、代わって個人としての機動性を意味する Mobility (行動の制約からの自由)が台頭する(バブル崩壊後・少子高齢化時代の日本、近い将来のドイツ、イタリア、スペイン、韓国)。
そして、社会の高齢化が更に進み、情報技術と物流効率によって地域格差がなくなると、Mobility (行動の制約からの自由)の意味も薄まり、Ability (意思の制約からの自由)の価値が高まる。自ら動くこと(Mobility)を助けてくれるモノよりも自分に代わって動いてくれるヒトのありがたみが増すのである。従来は自ら動かない限り、ぼんやり「思う」だけでは叶わないからと「意思」にすることすら諦めていたことが叶うようになるという意味で「意思の制約からの自由」(Ability)なのである。
自動車のみならずヘリコプター輸送やマリーナ経営も行なうなど Mobility(行動の制約からの自由)の価値提供段階にあるトヨタが、人間の Quality (生き方の制約からの自由)を高めるために次はパートナー・ロボットによるAbility (意思の制約からの自由)だと考えて、ソニーからロボット犬「AIBO」の技術を買収し、技術シーズを強化したことは自然な進化のプロセスだと考えられる。サンドバギーを作り、エアタクシー事業にも参入したホンダが二足歩行ロボット「ASIMO」に取り組んでいることも同じ文脈で捉えられる。
【新規事業開発の背景と動機付け】
織機から発展して自動車、住宅、情報と事業ドメインを広げてきたトヨタは伝統的に新規事業開発に熱心な企業である。だが、それはトヨタが新規事業を許容できる事業規模と収益力を持っているから、つまり余裕のある大企業だからこそできることだ、とする意見がある。本当にそうだろうか。
トヨタが世界の中で規模的・収益的に存在感を高めたのは 70年代・ 80年代のことである。69年に創業以来の累計で 100 万台に過ぎなかった輸出台数が 6年後の 75年には 500 万台、さらに 4年後の 79年には 1000 万台、その 6年
後の 85年には 2000 万台と、加速度的に事業規模を拡大していく。マスキー法とオイルショックが引き起こした米国での日本車ブームに乗り、プラザ合意(85年 9月)前の円安にものを言わせて、言葉は悪いがトヨタが対米輸出で荒稼ぎして急成長した時代である。
もし、企業規模や収益性が新規事業開発の意欲や能力を高めるのであれば、この時期に新規事業が次々に生み出されていてもおかしくない。
トヨタが 50% 以上の議決権を持つ子会社は国内に現在 63 社あるが、そのうち 70年代・ 80年代の 20年間に設立されたものは 4 社しかない。 その前の 40年代・ 50年代には 7 社ずつ、60年代には 10 社が設立されていること、また、その後の 90年代・ 2000年代(2007年時点)には 12 社ずつが設立されていることと比較すると、70年代・ 80年代の会社設立数の少なさは際立っている。
新会社の中にはトヨタ自動車九州のような自動車事業本体のための会社も含まれ、また、新規事業の中には会社設立を伴わずに事業部で行なわれているものもあるから、必ずしも会社設立数=新規事業開発件数とは言い切れないが、凡その目処として考えれば、事業規模や収益力の拡大期には新規事業開発が停滞していたことになる。
(なお、トヨタ第二の創業といわれる住宅事業(現トヨタホーム)は 75年に発足した住宅事業部が直接の母体だが、その起源は 46年に豊田喜一郎元社長の発意で生まれた豊田総建もしくは 50年設立のユタカプレコン(現トヨタ T&S 建設)にあることから、70年代の新規事業には含めていない。)
40年代はトヨタが経営危機に直面した時期であり、乗用車メーカーとしての体裁が整ったのは 55年のクラウン、66年のカローラ以降のこと(そもそもこれら乗用車事業への進出自体が当時で言えば新規事業であった)だから、60年代までのトヨタには常にリスクが内包されていた。
また、90年代に入ると、ピーク(1990年)時には 777 万台を数えた国内新車市場がバブル崩壊と人口動態の変化により長期下降トレンドに陥り、90年代末時点で既にピーク時から約 200 万台も減少しており、特に登録車だけを見るとピーク時の 3分の 2 の市場規模に縮小している。海外メーカーのコスト・品質面でのキャッチアップが表面化し、日本車の4つの過剰(設備・雇用・設計・品質)・円高・経済摩擦(とそれに伴う海外への生産移転)により輸出競争力が急速に失われたのもこの時期で、1985年には 700 万台近くあった輸出が 90年代半ばには約 300 万台も減少した。さらに、90年代末から 2000年代前半にかけては、世界的に「400 万台クラブ」旋風が吹き荒れ、殆どの日本車メーカー
が外資の日本工場化するのではないかと恐れられた時期でもある。
(ここら辺の自動車産業史は本誌バックナンバー『2007年に始まる新たな自動車産業史と戦略を考察する』をご参照いただきたい。)
前編:『2007年に始まる新たな自動車産業史と戦略を考察する』
後編:『2007年に始まる新たな自動車産業史と戦略を考察する』
トヨタが新規事業開発を積極的に進めた時期は、必ずしも事業規模・収益力が拡大した時期と重なっているわけではなく、反対に自動車事業存続の危機を感じ取った時期にこそ新規事業開発が行なわれてきたということができる。
では、危機感だけで新規事業開発が行なわれたのかといえば、必ずしもそうではなさそうである。
89年には事業開発部を創設して、自動車事業の関連・周辺分野や新たな Mobility分野での新規事業開発のテーマを社内公募し、社内ベンチャーの設立を奨励した。95年には起業家制度を導入し、96年にはトヨタベンチャーファンドを設立している。
その結果、早くも 90年にはベンチャー第一号として、信越化学工業との合弁により自動車の関連・周辺領域で先端材料開発を行なう子会社アドマテックスが設立されている。また、Mobility の延長線上にあるものとして、93年にはマリーナ(個人用ヨットの母港)経営を行なう子会社長崎サンセットマリーナが設立され、97年には西武グループから朝日航洋を買収してビジネスジェット・ヘリコプターでの航空輸送・測量事業に進出している。
90年代以降に子会社数の増加速度が急激に上昇したことは前述の通りである。
また、新規事業とは少し毛色が異なるかもしれないが、環境企業としての名声を確立した HEV のプリウスが発表されたのが 97年、第三の創業である情報事業のガズーメディアサービス(現デジタルメディアサービス)が設立されたのが 2000年である。
つまり、90年代以降の新規事業は、危機感を背景としつつ、そこに組織的な動機付けを加えることで活性化してきたものではないかと考えられる。(この時期には新規事業開発に限らず危機感と組織的動機付けによる企業変革が推進された。92年には商品開発センター制を導入して主査制を再強化して新商品開発力を劇的に高めた。また、2000年には組織横断的なコスト低減活動「CCC21」がスタートし、コスト競争力を抜本的に再強化している。)
【新規事業開発の目的】
このように組織的に啓発されてきた新規事業群は現時点で全社的にどのような意義を持っているのかを検証してみたい。
07年 3月期の連結財務諸表によると、トヨタの連結売上高 23.9 兆円のうちトヨタ自動車単体の寄与分は 11.5 兆円で全体の 48 %を占めている。
残り 12.4 兆円(52 %)が子会社の寄与分ということになるが、このうち最大の「金融事業」(トヨタファイナンシャルサービス等)でも売上高 1.3 兆円(5 %)に過ぎない。次いで、「第二の創業」である「住宅事業」(トヨタホーム等)が来るが、売上高は一桁小さい 15 百億円(0.7 %)に過ぎない。「第三の創業」である「通信事業」(デジタルメディアサービス等)の売上高は 6百億円(0.2 %)と更に一桁繰り下がる。「非自動車事業」全部を合わせても連結売上高への貢献は 2 兆円(9 %)に留まる。
結局、子会社の連結売上高寄与分の多くは、自動車事業(売上高 10.3 兆円・43 %)から来ており、その半分は自動車本体の製造業 4 社、つまりダイハツ工業(1.6 兆円・ 7 %)、トヨタ車体(1.4 兆円・ 6 %)、日野自動車(1.3 兆円・ 5 %)、関東自動車工業(0.7 兆円・ 3 %)からもたらされている。(注・内部消去はここでは捨象している)
同様に連結営業利益への貢献度合いを見てみると、トヨタの連結営業利益 2.2 兆円のうち、単体の寄与分と子会社の寄与分はともに 1.1 兆円(正確には単体 51 %対子会社 49 %)である。
売上高で見たのと同様に、子会社の利益貢献 1.1 兆円のうち 0.8 兆円はダイハツや日野など自動車事業子会社からもたらされたもので、「非自動車事業」の貢献分は 0.3 兆円(全体の 14 %)に過ぎない。その殆どは「金融事業」(0.3 兆円・ 13 %)によるものであり、「住宅事業」は 177 億円(0.8 %)、「通信事業」は 81 億円(0.4 %)の寄与に留まる。「その他の非自動車事業」は 38 億円(0.2 %)のマイナス貢献になっている。
ゼロから立ち上げた新規事業の数字としては立派なものだが、全トヨタへの寄与度は小さい。もちろん、自動車事業の好調により新規事業の貢献割合が小さく見えるということはあるものの、一方で新規事業の売上・利益の大半を占める「金融事業」が自動車販売金融に依存していることを考えると、少なくとも新規事業がトヨタから「モーター(自動車)」という文字を取り払っても同社を支えていけるような存在、事業規模にまで育っているとは言えないだろう。
では、新規事業開発は無意味だったのかといえば、全く逆だと考える。というのも、新規事業開発の目的が全社的な収益力の強化や補完に限定されていたわけではなく、寧ろ全く別のところにあったとも考えられるからである。
新規事業開発の真の目的は人材開発にあったのではないかと筆者は推察する。
自動車事業に関わる人材には専門性と同時に統合性が要求されるようになってきたが、後者の属性を養成する場面が自動車事業の現場から失われ始めているために、その補完策として有効な手法の一つだという認識があったのではないかと思うのである。
自動車という製品や事業に関わる人材に要求される専門性が高まってきたことは言うまでもない。
かつては QCD が製品や自動車事業者の役割・責任として必要十分であった。
だが、QCD は、必要条件としての要求水準が高度化したうえに、十分条件ではなくなった。自動車という製品に対しては人の生命・健康や地球環境、天然資源に与える影響を極小化する技術・装備・性能・機能が、自動車事業者に対しては法規制の枠組みを超えたレベルでの倫理や説明責任・統治責任が求められるようになったからである。自動車に対する完全性の要件が高まったのである。
完全性要件が高まったことで、自動車事業者は組織・人事・プロセスを細分化し、各々の専門性を高めることを余儀なくされる。個々の人材には細分化された業務範囲で高度な専門性を発揮することが求められるようになる。
ところが、自動車事業に関わる人材には領域を跨った全体最適の視点や統合的な思考も同時に求められるようになったのである。
かつては、生産と販売の一部機能の海外移転にとどまっていたグローバル化が本格化して、商品企画、デザイン、製品・技術開発、調達、ディストリビューション、販売金融、サービス、リマーケティングなどサプライチェーン全域はもちろん、法務・労務・財務も含めた企業の殆どの機能が海外移転されるようになったため、機能別の組織群や個別の商品群、複数のブランド・グループを貫いて地域軸で事業全体を一体として見渡せる人材が必要になってきた。
完全性要件はもはや個別の構成部品単位では達成できない水準にあるから、モジュールやシステムの括りで、あるいは材料や構造に遡った次元で、統合的にものづくりを考えられる人材が求められるようになった。
また、ものづくりの現地化を進めるにあたって現地の文化・価値観や経済発展段階・社会構造によっては国内の基準やプロセスをそのまま持ち込んだのでは却って生産性や品質が低下するようなケースもあるから、現地事情に応じたものづくりの最適化ができる柔軟性のある人材が必要になっている。
さらに、完全性要件を満たすため、自動車という製品が技術的に高度化・複雑化した結果、ブランドというシグナルで商品が選ばれる傾向(情報の非対称性)が強まり、ブランドの軸で商品戦略や地域戦略、組織戦略全体を一元的に考えられる人材のニーズが高まってきた。
このような専門性と同時に統合性を持った人材の開発という課題に対して、自動車産業では、伝統的に主査制(プロジェクト方式での組織横断的な商品開発制度とプロジェクトリーダーへの包括的な権限委譲)や計画的な人事ローテーション、コスト革新などの課題別タスクフォースの編成等、現場での OJT で乗り切ってきた。
だが、組織の細分化や専門化が進み、事業規模の拡大とともに企業の社会的責任が高まった結果として、守備範囲を超えて若手に全体を任せることの不安が生じてくる。
一方で、広範な業務経験を持ち、若手の指導者として期待できるベテランは退職期が近づき、数が減少してきた。結果として、若手が統合性・全体最適の視点を養う機会が減ってきている。結局、社長と主査など幹部になるまで全体が見えなくなり、全体が見えない人材が幹部になってしまうという恐れが出てくる。
自動車事業本体ほどには投資やリスクの負担がない領域で効率的に統合性や全体最適の視点を持った人材を開発する機会として、新規事業開発が活用されているとも考えられなくない。自動車事業の周辺や延長線上の領域での新規事業開発というプロセスを通じて、将来の自動車事業を担う幹部候補生に事業全体を担う経験を積ませるという考え方である。
【新規事業開発の問題点と解決策】
人材開発を実質的な目的とした新規事業開発の最大の問題点は、「お互いの甘え」による「イノベーションの生まれにくさ」にあるとされる。
裏の目的が何であろうと、事業として行なう以上、事業成果が求められるはずである。大企業の社内ベンチャーや 100 %子会社という形態を考えると、そこに投入される人材が個人の財産の放出や、個人保証の差入れ、雇用保証の放棄を求められることはないという意味でセーフティ・ネットが存在するのが普通である。セーフティ・ネットのもとでの事業経営には気概・気迫の面で甘えが出易く、構造的に成果達成の水準やスピードが下がり、イノベーションが生まれにくいという指摘がある。
また、親会社の側にも甘えが生じやすいとされる。仮に社内ベンチャーがカーブアウトや独立法人の形態を取っていたとしても、そこにいるのが部下・同僚ばかりだとすれば、実質的には社内組織の一部・下部組織の一つと見なして株主の立場を超えた干渉をしがちになる。新規事業開発に必要な独立性が担保されないから、やはりイノベーションが生まれにくいと言われる。
だが、セーフティ・ネットのもとでの新規事業開発からはイノベーションが生まれにくいというのは本当だろうか。 日本に比べて圧倒的にベンチャーの起業件数が多い米国では、税制にも支えられてエンジェルが資金面でのスポンサーになってくれるから、起業家が皆自己資金や個人保証を差し入れなければいけないわけでもなく、当座の資金繰り
や自己破産を気にすることなく、大きなテーマへの挑戦や顧客・社会の利益を
第一義に置いたオペレーションも可能になる。
事業に失敗しても皆が自己破産に追い込まれるわけではない。万一、失敗や破産に追い込まれてもそれが犯罪のように社会的に制裁される日本と違って、挑戦と失敗の経験を持つ元ベンチャー経営者には教訓を活かした再挑戦の誘いも多い。
但し、ステークホルダーに対する説明責任はある。見ず知らずの第三者にスポンサーになってもらうわけだから、寧ろそれが全てとも言える。
つまり、米国では社会的なセーフティ・ネットが存在するからこそ大きなイノベーションが生まれているわけで、日本では社会に代わって大企業がセーフティ・ネットを提供しているのだと考えれば、それ自体が問題なのではない。問題は、「説明責任」と「独立性の担保」にあるということになる。
そこで、僭越ながら弊社のケースをお話ししたい。弊社は合弁資本の会社であり、人材的にも両株主の人間をミックスするとともに外部からも採用している。異なる血を混ぜ合わせることで説明責任と独立性を強化・保証し、セーフティ・ネットの存在によって「自動車から始める日本のイノベーション」という社会的テーマの実現を目指した顧客本位のオペレーションが可能になったのではないかと思っている。
合弁事業とした理由は、正に「説明責任」の強化と「独立性の担保」である。
100 %子会社の場合は、どうしても一人息子と母親のような濃密な関係になるが、合弁事業の場合は、特定の株主だけに説明責任を果たせばいいということにはならない。逆に親会社の側も自社のロジックの押し付けはできない。顧客の機密を預かる弊社の事業の特性を考えれば、独立性の確保による親会社との情報の遮断は顧客の利益のために不可欠なことでもあった。 また、多様な人材をミックスすることで、内部的にも説明責任や独立性が強化された。別々の風土で育った別々の価値観を持つ従業員に対しては独立会社としてのミッション、ビジョン、戦略を語り、納得と同意を得ない限り、人は動かず仕事にならないという緊張感が維持されるからだ。
トヨタの新規事業開発の歴史を見ても事業開発とともに合弁で新会社を設立した事例が散見され、事業成果を上げているところも多い。
前述のとおり、新素材開発のアドマテックスは信越化学工業との合弁企業だが、売上高 70 億円、営業利益 20 億円を上げるまでに成長している。三菱商事との合弁で設立した医薬品卸・病院経営コンサルティング子会社グッドライフデザインは設立 3年で売上高 40 億円に達し、当期利益で数千万円のレベルをキープしている。リクルートとの合弁でトヨタ生産方式のコンサルティングを行なう OJT ソリューションズは、2002年の設立以来、バックオーダーログが多すぎて仕事を断るのが営業の仕事になっているような状態だと聞く。
大企業が行なう人づくり目的の新規事業開発は、血を混ぜ合わせることによって説明責任と独立性の担保の問題を解決できれば、日本型イノベーションの宝庫ではないかと考える。「自動車から始める日本のイノベーション」のために大企業のアクションに期待したい。
<加藤 真一>